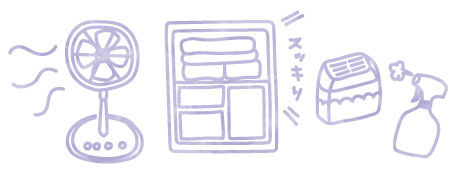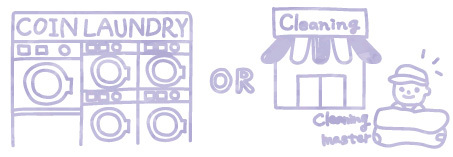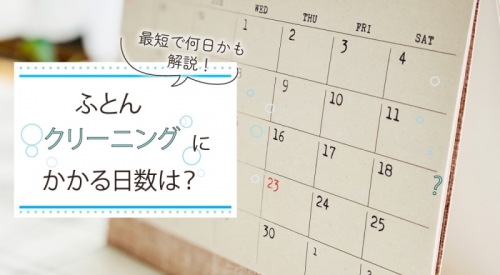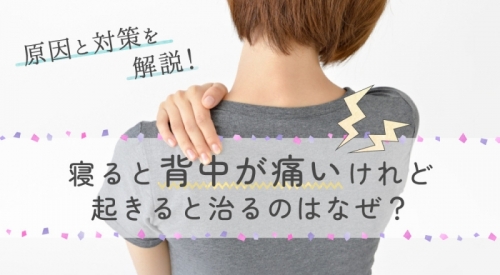押入れの臭いは何が原因?臭い対策やふとんに移った場合の除去方法もご紹介

|
|
執筆者情報:軽石 瑞穂 【業務内容】 おうちdeまるはちWEB関連運用 |
| 長年ふとんクリーニングや寝具のメンテナンスに携わり、お客様の快適な睡眠環境をサポートしてきました。安眠インストラクターや快眠セラピストなど睡眠に関する専門知識を活かし、ふとんクリーニングの重要性や家庭でできる快眠のヒントなど皆様の睡眠の質を向上させる為の情報をお届けします。 |
押入れから原因不明の臭いがしたときは
「臭いの原因は何?」
「収納してあるふとんにも臭いが移るのではないか?」
と不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
押入れの臭いには、カビやホコリなどさまざまな原因が考えられますが、早めに対処すれば臭いを取り除ける可能性があります。
この記事では、押入れの臭い対策やふとんに臭いが移ってしまった場合の対処法なども含めてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
|
押入れの気になる臭いの原因は?
「普段押入れに収納しているふとんや衣類から嫌な臭いがする」というときは、押入れ自体が原因である可能性が高いと考えられます。 では、押入れの臭いの原因は一体何でしょうか。 原因として考えられるものをご紹介します。
押し入れ内で繁殖したカビ押入れの臭いの原因は、多くがカビによるものといわれています。 カビは絵の具や墨汁のような臭いに似ているため、押入れからそのような臭いがするときはカビが繁殖している可能性があります。
カビが繁殖しやすいのは、湿度が70%・気温が15℃以上で、栄養源となるホコリや汚れなどがある環境です。 普段ふとんや衣類などを入れて閉め切っていることが多い押入れの内部は湿度や温度が高くホコリも溜まりやすいため、カビが好む環境になりやすい特徴があります。
押し入れ内の汚れやホコリ押入れは頻繁に掃除する場所ではないため、ホコリが溜まって臭いの原因になりやすいことも特徴の1つです。
また、食べカスなどの汚れが付いたままふとんや衣類などを収納すると、その臭いが押入れに染み付いてしまうこともあります。
ホコリや汚れが臭いの直接的な原因になるだけでなく、それを栄養源として増殖するカビの臭いも強くなる可能性があるため、 しっかりと対策しておくことが大切です。
木部の劣化古い押入れの場合は、木部の劣化が臭いの原因になっている場合もあります。
押入れはほとんどが木材でできており、湿気やカビなどが原因で劣化が進むとそれ自体が臭いの発生源になってしまいます。 木材の劣化は放っておくとどんどん進行し、改善させるためには新しい木材と交換するしかありません。
手遅れになる前に気付けるよう、普段からこまめに押入れ内の状態をチェックしましょう。
水漏れの可能性押入れのカビ臭さが改善されない場合は、雨漏りの可能性も考えてみましょう。 押入れの上の天井が雨漏りしていると、雨水が侵入して水浸しになることがあります。 雨漏りが悪化すると、押入れの中の衣類や寝具などにも被害が及ぶ可能性があるため、注意が必要です。 雨漏りが疑われる場合は、速やかに修理を依頼することが重要です。 また、押入れの内装をリフォームすることで湿度を調整することができる場合もあります。 例えば、襖の張り替えなどがその一例です。
押入れのカビを除去するには?
押入れの臭いの原因として特に多いといわれているカビは、早めに除去する必要があります。 押入れにカビを発見した場合の対処方法をご紹介します。
表面の白カビはエタノールで除去アルコールの一種であるエタノールの中でも、消毒用エタノールはカビを死滅させる効果が強いことで知られています。 「黒ずみはないが押入れからカビの臭いがする」というときは、押入れ全体に消毒用エタノールを吹きかけてカビを除去しましょう。 目に見えていなくてもカビの胞子が広がっている可能性があります。
まずは押入れの中身をすべて出して空の状態にしてから、固く絞った雑巾で押入れ内のホコリを拭き取ってください。 このとき、カビの胞子を吸い込んでしまわないようマスクを着用し、換気をしながらおこなうことが大切です。
消毒用エタノールを吹きかけたら、蒸発するまでしっかりと乾かします。 完全に乾いたら、押入れの中に荷物を戻しましょう。
黒ずみは次亜塩素酸ナトリウムで除去カビによる黒ずみが発生している場合は、酸性の次亜塩素酸ナトリウムを使って中和させましょう。 漂白作用はないため黒ずみは残りますが、カビを死滅させてそれ以上広がるのを防げます。
まずは、押入れの中身をすべて出し、換気をしてマスクを着用しながら、固く絞った雑巾で押入れの中を拭いていきます。 次に400ppmの次亜塩素酸水を用意します。 店舗によっては最大濃度が200ppm程度のこともありますので、濃度に注意して購入してください。 400ppmの次亜塩素酸ナトリウムをスプレーボトルに入れて押入れ内に吹きかけてください。 固く絞った雑巾でしっかりと拭いてからよく乾かしましょう。
似た名前のもので次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする塩素系漂白剤がありますが、これだと最後に洗い流す必要があるため、押入れのカビ取りには適していません。 間違えないように注意してください。
押入れの臭いに有効な5つの対策
押入れの臭いが気になるときに試してみたい対策を3つご紹介します。 臭いの予防にもつながるため、普段から心がけておくと安心です。
定期的に換気をおこなう押入れの臭い対策には、定期的な換気が効果的です。 湿気が溜まらないように、こまめに襖を開けて風を通してあげましょう。 特に、湿度が高くなりやすい梅雨時期は押入れの中にもカビが発生しやすいため、注意が必要です。
収納してあるふとんや衣類なども、定期的に押入れから出して天日干しをしましょう。
また、押入れ内で空気の通り道を作るために、そこに「すのこ」を敷いてからものを収納する方法もおススメです。
頻繁に掃除をする定期的な換気に加えて、頻繁に掃除することも大切です。 押入れの内部が汚れていると、そこはカビが繁殖しやすい環境になります。頻繁に掃除をしてカビの発生源を取り除くことが大切です。 できる限り、定期的に押入れの中の寝具や衣類をすべて取り出して掃除するのがおススメです。
これによって、押入れの内部を徹底的に清潔に保ち、同時にカビの発生をチェックすることができます。
荷物の量を減らす押入れの中に物を詰め込みすぎると、空気の通り道がなくなって湿気が溜まりやすくなります。 物をぎゅうぎゅうに詰め込んでしまっている場合は、この機会に不用品を処分して物を減らしてみてはいかがでしょうか。
荷物が減れば押入れ内のスペースに余裕ができるため、掃除もしやすくなります。 ホコリが溜まりにくくなればカビの増殖も防げるはずです。
まずは押入れの中の物をいったん取り出し、「必要なもの」と「不要なもの」に仕分けしていきましょう。
消臭グッズや防カビグッズを活用する市販の消臭グッズや防カビグッズも積極的に活用してみてください。 消臭剤は置くタイプや吊るすタイプ・スプレータイプなどさまざまな種類のものがあるため、使いやすいものを探します。
また、湿気やカビ菌を分解する防カビ剤なども市販されているため、同時にチェックしてみましょう。
家中のお掃除に使える重曹も、押入れの消臭・防カビに役立ちます。 重曹には消臭・吸湿効果があるため、嫌な臭いを消してくれるだけでなく、カビの原因となる湿気を吸い取ってくれます。
着用した後の衣類をしまう際はできるだけ清潔に保つ1日着用した衣類には、目に見えない汗や皮脂汚れ、ホコリなどが付着しています。 そのまま収納すると、カビやダニの発生、衣類の変色や劣化の原因となる可能性があります。 洗濯可能な衣類は洗濯し、クリーニングが必要なものはブラシで汚れを取り除いて乾燥させた後に収納しましょう。 洗濯が難しい場合は、一旦押入れ以外の場所で、清潔に保つようにしましょう。
押入れのふとんが臭いときの対処法
押入れの臭いが収納していたふとんに移ってしまうこともあります。 押入れから出したふとんの臭いが気になったときの対処法をご紹介します。
カバーやシーツを洗うふとんカバーやシーツに臭いが染み付いている場合は、洗濯で落とせる可能性があります。 通常の洗濯物と同じように通常コースで洗える場合がほとんどなので、こまめに洗濯しましょう。
ふとんカバーやシーツにカビが生えているようなら、酸素系漂白剤を使って除去する方法がおススメです。 大きめの桶に40~60度のお湯と酸素系漂白剤を入れ、その中でふとんカバーやシーツを1時間ほど漬け置きしてください。 その後、通常通り洗濯し、外に干して日光消毒すれば完了です。
ふとんを干すカバーやシーツだけでなくふとん自体の臭いも気になるようなら、ふとんを外で干して日光を当てましょう。
太陽の光に含まれる紫外線には殺菌効果があり、細菌の繁殖を防いでくれます。 しっかりと乾かすことでカビの発生原因である湿気もなくせるため、臭いの発生を防ぐことにもつながります。
外に干すのが難しい場合は、窓を開けて部屋を換気した状態で室内用の物干しにふとんを掛け、日の当たる場所に干すだけでも効果的です。
ふとんにカビが生えている場合は除去するふとんにカビが生えているのを発見した場合は、重曹水とエタノールを使って除去できます。
まず、100CCの水に重曹小さじ1杯を溶かし、スプレーボトルに入れます。 カビが生えている部分に重曹水をスプレーし、5分ほどそのまま放置しましょう。 重曹水によってカビが浮いてくるため、キッチンペーパーで拭き取ってください。
次に、エタノールを吹きかけてカビを死滅させたら、ふとんを外に干して日光消毒して完了です。
ふとんにカビが生えた場合の対処法については、こちらの記事も参考にしてください。
自宅でふとんの洗濯が難しい場合には
「自宅の洗濯機に入りきらない」「洗濯しても干す場所がない」などの理由でふとんの臭いを自分で取り除くのが難しい場合は、次のような対処法を検討しましょう。
コインランドリーを活用する水洗いが可能な素材のふとんであれば、コインランドリーが活用できます。 コインランドリーにはふとんを丸ごと洗濯できるサイズの洗濯槽があるため、持ち運びさえ可能であれば簡単に洗濯できます。
自宅での洗濯だと完全に乾くまで何日も干しておかなければなりませんが、コインランドリーの高温乾燥機を利用すれば数時間で乾燥まで終わらせることが可能です。 高温乾燥はカビ予防にも効果的なため、臭いに悩まされることもなくなるのではないでしょうか。
ただし、素材によってはコインランドリーで洗えないふとんもあるため、事前にしっかり確認することが大切です。
ふとんのクリーニングを依頼する自己流の洗濯では不安な素材のふとんや、洗濯しても落ちないカビが付着している場合などは、ふとんのクリーニング業者に依頼するのがおススメです。 宅配サービスをおこなっている業者なら自分でふとんを持って行ったり取りに行ったりする必要はありません。
ふとんのクリーニング業者をお探しなら「おうちdeまるはち」をぜひチェックしてください。 おうちdeまるはちのふとんクリーニングのこだわりはこちらの記事からご覧いただけます。 「シリーズ企画:おうちdeまるはちふとんクリーニングのココがポイント! 水へのこだわり編」 「シリーズ企画:おうちdeまるはちクリーニングのココがポイント! 洗浄のこだわり編」
さらに抗ウイルス加工や防ダニ加工などのオプションサービスも用意しているため、臭いが気になるふとんも清潔な状態に生まれ変わります。
また「オフシーズンの間、ふとんを押入れに入れておくと臭いが付きそうで心配」というときは、長期保管サービスの利用もおススメです。
まとめ
押入れの臭いの原因やカビが発生している場合の除去方法・押入れの臭い対策などをご紹介しました。
押入れに収納してあるふとんや衣類などに臭いが移ってしまうと取り除くのが大変になるため、早めに対処することが大切です。 特に、ふとんは自宅での洗濯が難しく、臭いを除去するにはふとんクリーニングへ依頼することも検討してみてください。
また今回の記事ではふとんクリーニングを活用するメリットも掲載しているため、下記にご紹介する記事もあわせて、ぜひ参考にしてみてください。 |
|
関連記事 |
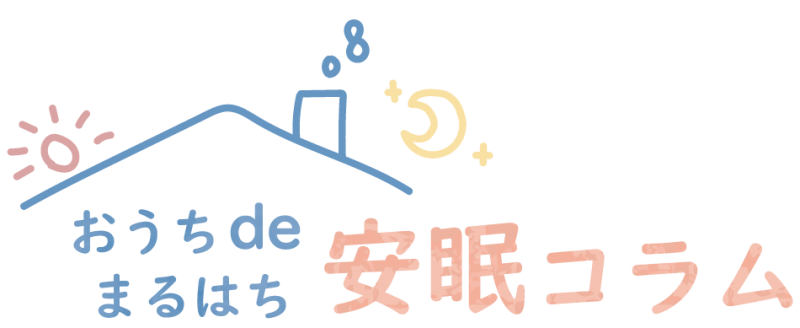 寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載
寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載
新着記事