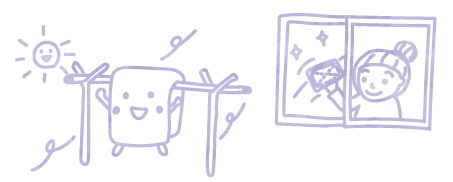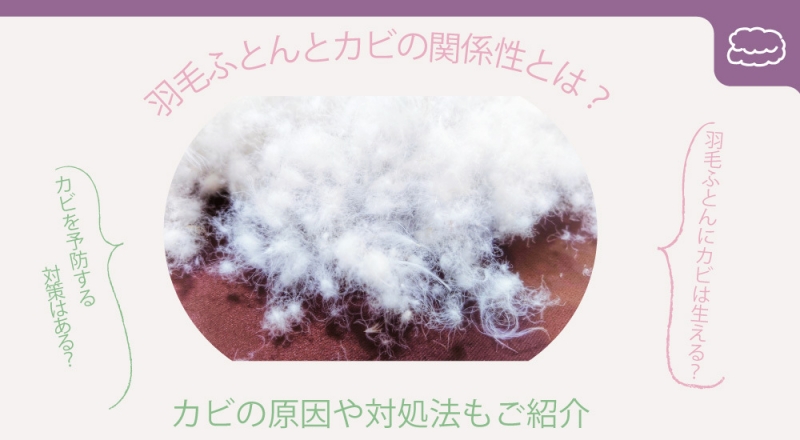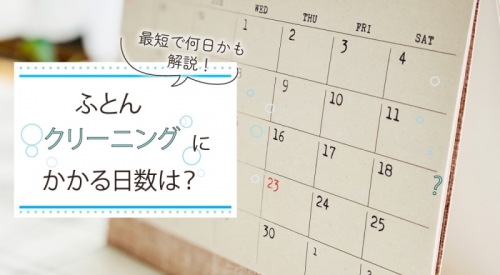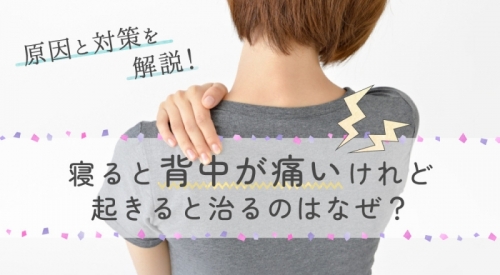|
ふとんにカビが生える原因

カビは、温度と湿度の条件がそろうと発生し、ゴミなどを養分として繁殖します。
寝具は人の体温で温められるうえに、寝汗が染みこんで湿気がこもりやすく、さらにはカビの養分となる皮脂や髪の毛が付着するため、カビが発生・繁殖する条件を満たしてしまうのです。
また、カビは気温が20~30℃のときに繁殖します。これは人が過ごしやすいと感じる気温とほぼ同じです。
特に、カビの繁殖が活発になる温度は、25~28℃とされています。
そしてカビは湿度60%以上で活発になり始めます。
そして70%以上で繁殖し、80%を超えるとさらにその勢いを増します。
さらにカビは有機物を栄養にして繁殖します。
そのため、ふとんの埃や繊維などに汚れがあることで、さらにカビが生えやすくなってしまうのです。
ベッドや押し入れでもカビは生える!
ベッドなら、カビは大丈夫と思っていませんか?
実は部屋全体の湿度が高く、結露がたまりやすいお部屋だとベッドでもカビは発生します。
特に冬場は外気と室温の温度差が原因で窓に結露が発生し、部屋全体の湿度が高くなってしまいます。
また、日当たりの悪いお部屋は日中でも太陽の光が当たらないため、マットレスの湿気と窓の結露は乾かずに再び夜を迎えて湿気がたまりカビが発生する要因になります。
あまり意識されませんが、ベッドのマットレスにはほとんど鉄製のスプリングが入っています。
スプリングそのものはカビにくいですが、覆っている布部分は注意しておかないとカビてしまうことがあります。
また、敷きふとんをそのまま敷いて寝るタイプのパイプベッドフレームや収納付きのベッドフレームだと湿気の逃げ場が少なくなるため注意が必要です。
さらに押入れに入れっぱなしで温湿度が高い状態でふとんを保管しておくとカビが生えることも。
暗くて閉めきった状態の押し入れは湿度と結露がたまりやすいので、このような環境にふとんを収納したままにすると、押入れだけでなくふとんにもカビが生えてしまいます。
ベッドを使用しているから、押入れに入れているだけだから・・・という認識でいる間にカビの繁殖が広がっている可能性があるので注意が必要です。
ふとんに生えたカビは放っておいたら大変!

では、ふとんにカビを見つけた場合、どう対処すれば良いのでしょうか。諦めてそのままにしておいても大丈夫でしょうか。
カビを放置してしまうと様々な問題に繋がってしまう可能性があります。
カビは臭いに加えて咳やアレルギーの引き金にも
カビを放置すると、睡眠中にカビを吸い込み、咳やアレルギーを引き起こす原因にもなります。
特にカビの生えたふとんを免疫の落ちている人や高齢者・赤ちゃんが使用している場合や近くに置いて寝ているなどの場合は注意が必要です。
ふとんやマットレスに生えたカビが自然になくなることはないので、カビを見つけた場合は放置せず、しっかり取り除くことが大切です。
カビに気付いたら早急に対処しましょう。
カビ臭さを感じたら、空気が滞りやすい場所やホコリがたまりやすい場所を重点的にチェックし、定期的に掃除を行い、カビの栄養源となるホコリを取り除くことが重要です。
また、カビはダニの餌にもなるため、寝具やフローリングなどがカビの発生源にならないようにすることが大切です。
フローリングにもカビが生えると思わぬ出費も
フローリングにカビが生えると、綺麗に拭き取れず、シミになったり、目に見えて白く変色してしまいます。
そのような場合、素人では手に負えず、フローリングの張り替えを考えなければなりません。
賃貸住宅に住んでいる場合、退去時に修復費用が発生することもあります。
フローリングを元の材料に戻すか、どのようなフローリングに変更するか、施工方法によっては数十万円かかり、大きな出費になります。
フローリングのカビ発生は、何としても防止したい問題です。
ふとんのカビに気が付いたときの対処法

毎日使用している寝具は、気が付かないうちにカビが発生していることがあります。
ふとんの裏面や敷いているフローリングやベッドフレーム部分をよく観察してみてください。
一見汚れと見間違うこともありますが、黒くポツポツとした斑点が発生していたら、まさしくそれがカビです。
睡眠中、ずっと身体に接している寝具にカビが生えていれば、健康上のリスクは高くなるといえます。
ここではそれぞれに生えてしまったカビへの基本的な対処法をご紹介します。
【ふとんへの対処法】
敷きふとんのカビ取りに必要なのは、次の4つのアイテムです。
・重曹スプレー(ぬるま湯100mlに重曹を小さじ1混ぜておく)
・エタノールスプレー(水20mlとエタノール80mlを混ぜたもの)又は市販のアルコール除菌スプレー
・スポンジ
・ティッシュやキッチンペーパー
次に掃除手順は以下の通りです。
①カビを水で拭き取る
まず、水で湿らせたティッシュやキッチンペーパーで表面のカビを拭き取ります。
拭き取ったティッシュやキッチンペーパーには胞子が付着しているため、すぐに捨てましょう。
↓
②重曹スプレーをかける
次に、カビが生えてしまったところに重曹スプレーをふりかけ、重曹の成分をカビになじませるために5分くらい放置してください。
放置すると重曹が胞子を浮かせ、簡単に落とすことができるようになります。
↓
③スポンジで撫で洗いをする
スポンジにも重曹水をつけ、軽く水分を絞ってから重曹スプレーで浮かせたカビを撫で洗いしましょう。
↓
④エタノールスプレーや除菌スプレーをかける
ふとん全体によくふきかけ、残っているカビ菌をしっかりと除菌します。
↓
⑤完全に乾くまで天日干しする
水分が残ったままにしてしまうと、湿気で再びカビが増殖してしまいます。
風通しのいいところで天日干しをして、完全に乾かしましょう。
頑固なカビにはふとん水洗いクリーニングがおススメ!
自分でカビを除去しきれなかった場合や完全に乾かすのが難しい場合はふとんクリーニングを依頼しましょう。
「おうち de まるはち」は、ふとんクリーニングの専門家がしっかり汚れの種類を見極め、丁寧に水洗いをしていきます。
カビは側生地も傷めるので、強く洗浄しすぎてしまうと逆効果です。
カビ発生による黒い斑点は、若干残ってしまうこともありますが除菌の効果はクリーニングすることで高くなります。
ふとんを傷めずにキレイにする、ふとん専用のクリーニング工場だからこそできる高品質な洗浄技術をご提供します。
スタッフがふとんの集荷にうかがう際、ふとんの状態を一枚一枚確認します。
そのとき、ふとんにカビの範囲や気になることなど遠慮なくご相談ください。
詳しく確認したい方はふとんクリーニングのページをご覧ください。
【マットレスへの対処法】
カビ専用の除去スプレーを使用すれば、簡単にカビの除去が可能です。
使い方はカビが生えた部分にスプレーを吹きかけて30分待つだけ。
落ちない場合は、何回か繰り返しスプレーしましょう。
スプレーした部分が乾けば除去完了です。
注意点としては、マットレスの布が色落ちしてしまう可能性があることです。
そのため、はじめに色落ちの確認をしてから使うようにしましょう。
また、酵素系の漂白剤を使えば、カビの殺菌、黒ずみの除去、さらには色落ちの心配までなくしてくれます。
これは商品ごとの説明をよく読み、希釈してスプレーボトルに入れて使用しなければなりませんが、効果は高いといわれています。
【シーツ・カバーへの対処法】
必要なのは、次の4つのアイテムです。
・酸素系漂白剤
・歯ブラシ
・ゴム手袋
・お湯
カバーやシーツが色物でなければ塩素系漂白剤を使用してもOK。
色や柄がついている場合は、色落ちしにくい酸素系漂白剤を使うことをおススメします。
掃除手順は以下の通りです。
①窓を開けてゴム手袋をつける
しっかりと換気された環境のもとで行うようにしてください。
↓
②漂白剤を溶かしたお湯につけ置きする
酸素系漂白剤は40~60度のお湯で溶かすことで効果を発揮するため、必ず水ではなくお湯を使いましょう。
↓
③1時間置き、残ったカビを歯ブラシでこする
酸素系漂白剤の除菌・漂白作用でほとんどのカビは落ちますが、残っている場合は歯ブラシでこすって落としましょう。
↓
④洗濯機に入れてから乾かす
カビと漂白剤をしっかりと洗い流すために、洗濯機で通常通り洗ってすすぎと脱水をします。
脱水が終わったら風通しのいいところで天日干しをして、カビ取り完了です。
【フローリングや畳への対処法】
床にまでカビが発生してしまったときは、住宅用中性洗剤とエタノールスプレーを使用することで除菌が可能です。
この時に掃除機はかけず、まずカビの胞子を拭き取ることが大切です。
いきなり掃除機をかけてしまうと、カビの胞子を部屋中に撒き散らしてしまうため、自分を含め周囲の人がカビの胞子を吸い込んでしまう可能性もあります。
まずは、住宅用中性洗剤をカビに吹きかけしばらく放置してから雑巾で拭き取り、エタノールスプレーで除菌した後、新しい雑巾で拭き取りましょう。
ただし、フローリングや畳は、洗剤やアルコールによって塗装が剥がれたり変色したりしてしまう危険があるので注意が必要です。
【すのこやベッドフレームへの対処法】
すのこや木製のベッドフレームにカビが生えてしまったら、アルコール除菌スプレーやエタノールをかけ、キッチンペーパーやティッシュなどで拭き取りましょう。
カビを拭ったものは1度で捨ててください。
カビを取り除いたら完全に乾燥させてからマットレスやふとんを敷きなおしましょう。
また、酸素系漂白剤を用いてもカビを落とすことができます。
漂白剤をキッチンペーパーなどに染みこませ、カビを覆いましょう。
その後、10分ほど放置してから硬く絞った雑巾や不要な布などで、漂白剤を拭き取ってください。
カビを取り終わったら完全に乾くまでそのままにしましょう。
日光にあてたり、風通しのよいところに置いておくほか、エアコンをドライにして乾かすのもおススメです。
ふとんや床のカビ予防に効果的な対策とは?
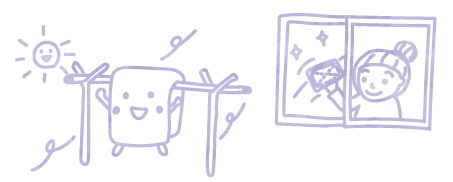
日常的に意識して対策を行うことでカビを予防することが出来ます。
具体的に効果の高い対策をみていきましょう。
ふとんを敷きっぱなしにしない
ふとんを敷きっぱなしにしているという方は、今すぐ万年床をやめましょう。
使わないときは畳んで、押入れなどにしまう習慣をつけるようにすることでカビが予防できます。
ただし、朝起きてすぐにふとんを畳んでしまうと湿気がこもってしまいます。
起きてから1時間くらいはふとんをめくった状態で放置し、湿気を逃してから収納することをおススメします。
朝に時間が無いという方は、起きたらすぐに扇風機をあてて、家を出る前に畳むなどの方法も効果的です。
ふとんの湿気を飛ばす
ふとんのふとんは1週間に1回は天日干しするようにしましょう。
表と裏を1~2時間ずつ太陽にあてるだけでも、カビの発生は大幅に抑えられます。
天日干しが難しいときは、室内で椅子やふとん干しラックなどにかけておくだけでもカビの予防が可能です。
また、ふとん乾燥機を使うのも効果的です。
マットレスを使っている方は、マットレスを立てて風を通すようにしてください。
マットレスの同じ面だけを使っているとそこに湿気がたまるため、定期的に身体が当たる面の上下を交換したり、両面使用可能なタイプであれば表裏を逆にしたりするローテーションを行うとよいでしょう。
シーツ・カバーを定期的に洗う
湿気と同じくらいカビの好物なのが、人間の皮脂や汗です。
シーツやカバーを交換しないでおくと寝汗による湿気だけでなくフケ、アカといった汚れがたまってしまいます。
少なくとも週に1回はシーツ・カバーを交換し、洗濯するようにしましょう。
敷きパットやベッドパットを使用する
汗を吸収してくれる敷きパッドやベッドパッドはカビ対策の強い味方です。
丸洗いできるものを選ぶと、手軽にいつでも清潔を保てるのでおススメです。
カビの増殖を促す皮脂汚れもキレイに洗って清潔に保つことができます。
特にウールは夏でも冬でも快適に過ごせる万能素材!天然の吸放湿効果で、いつでもさらさら快適に眠れます。
除湿シートを使用する
敷きふとんの下に敷いて使用する市販の除湿シートもカビ防止の効果があります。
ベッドの場合はマットレスの上に敷いて使用します。
吸湿性の高い繊維や素材で作られているため、たまった湿気をしっかり吸収してくれます。
ただし、除湿シートにたまった湿気をそのままにしておくと寝具と除湿シート両方にカビが生える可能性があり、危険です。
週に1度は干すようにしましょう。
部屋の換気と掃除をこまめにする
年間を通して部屋の換気と掃除を心掛けましょう。
暖房を使用する冬は室内の温度と外の気温差が激しいため、窓に結露がたまりやすい季節です。
結露がたまることで部屋の湿度が高くなり、カビの繁殖が進むことに繋がります。
こまめに窓を開けて空気を入れ換えたり、エアコンの除湿機能や除湿機を使ったりすると湿気を逃がすことができます。
また、結露をこまめに拭き取り、窓周りの掃除をすることも大切です。
ホコリや汚れをためないように普段から気を付けましょう。
保管方法を見直す
ふとんのカビは、保管中にも発生する可能性があります。
クローゼットや押入れの中は湿気がたまりやすいので、ふとんの保管方法を改善してみてください。
【カビを予防するふとんの保管方法】
1.ふとんを完全に乾燥させる
2.通気性の良いカバーや袋に入れる
3.収納時に除湿剤や備長炭を入れる
4.壁から少し離して収納する
5.定期的に乾燥・天日干しを行う
定期的にふとんを出して乾燥させることをおススメします。これにより、ふとんの湿気が除去され、耐久性が向上します。
まとめ

ふとんにカビが生えてしまうとジメジメした感触やイヤな臭いで寝心地が悪くなるだけはなく、アレルギー、咳などの症状を引き起こす原因にもなりかねません。
敷き寝具にはカビができやすい条件がそろっているので、普段からカビ対策をし、カビができたら早めの対処をすることで、衛生的に保つことができます。
効果的な対策としては、カビそのもの繁殖を予防するには天日干し、部屋の換気や掃除、シーツ・カバーの交換といった日々のお手入れが挙げられます。
同時に除湿効果のあるシートや家電製品を上手に組み合わせれば、より万全なカビ対策が行えるでしょう。
ぜひ毎日の眠りを快適にするため、今回ご紹介した対処法や予防対策を試してみてはいかがでしょうか。
|
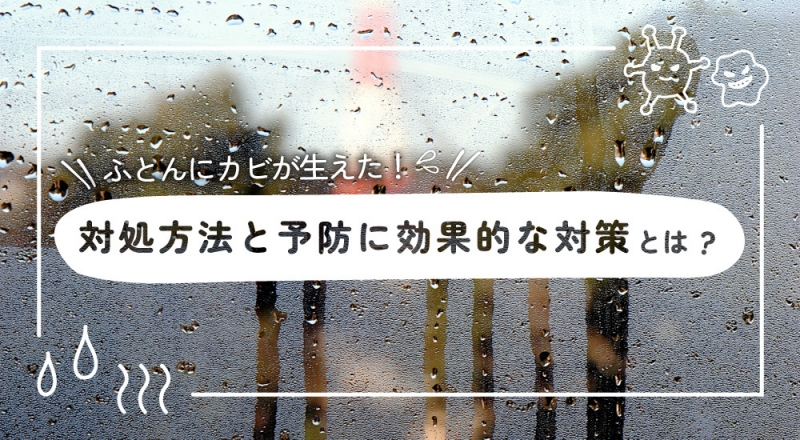
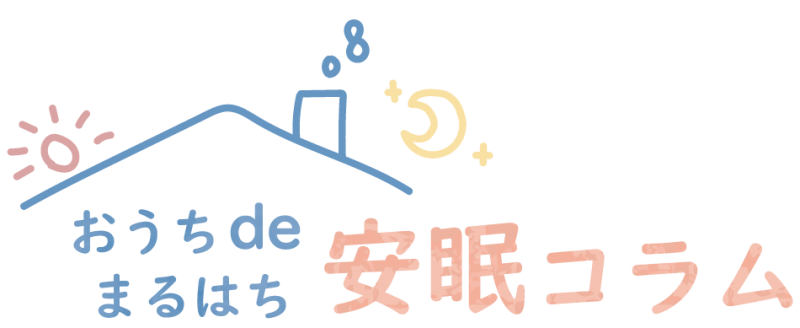 寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載
寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載