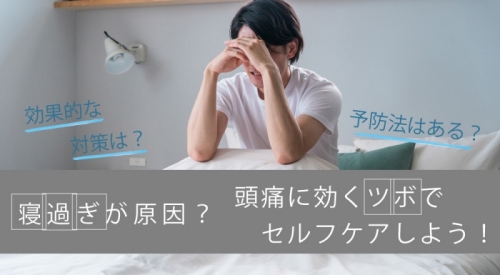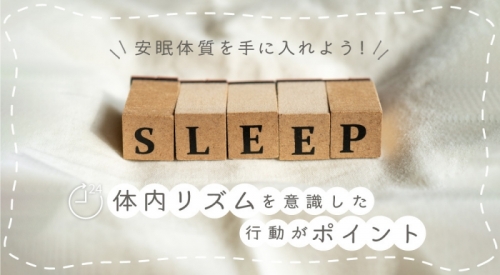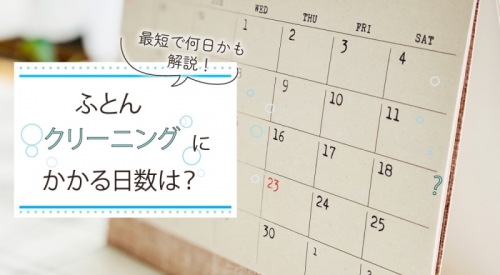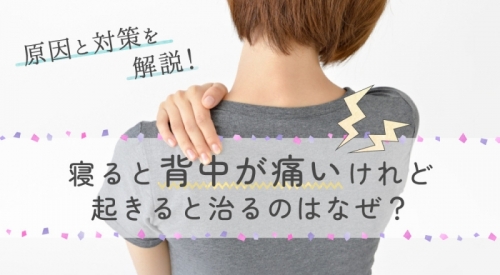年齢によって睡眠はどう変化する?基本的な知識やそれぞれの対策をご紹介
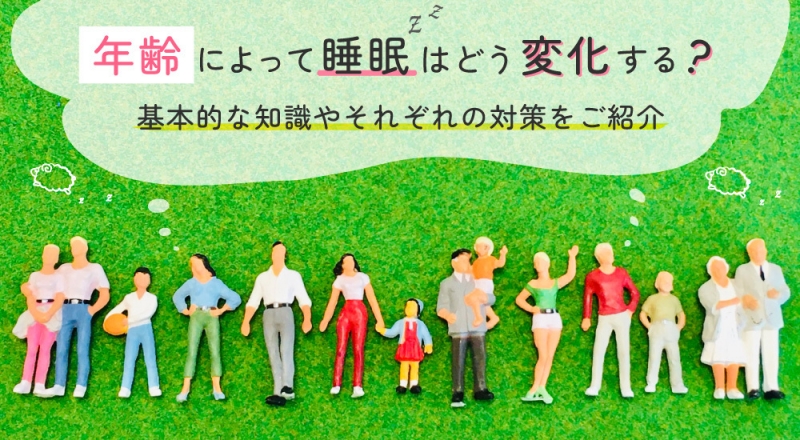
|
|
執筆者情報:軽石 瑞穂 【業務内容】 おうちdeまるはちWEB関連運用 |
| 長年ふとんクリーニングや寝具のメンテナンスに携わり、お客様の快適な睡眠環境をサポートしてきました。安眠インストラクターや快眠セラピストなど睡眠に関する専門知識を活かし、ふとんクリーニングの重要性や家庭でできる快眠のヒントなど皆様の睡眠の質を向上させる為の情報をお届けします。 |
睡眠は、単純に身体を休めるだけではなく、心身の修復や記憶の整理をしてくれます。
人間にとって生きていく上で欠かすことのできない時間ですが、実は睡眠は年齢を重ねるにつれて少しずつ変化していきます。
毎日当たり前のように眠っていますが、加齢とともに
「若いころは寝て起きたら元気だったのに・・」
「最近朝早く目が覚めてしまう・・」
といった疑問やお悩みが出てくるのは自然なことです。
このコラムでは年齢によって変化する睡眠についての基本的な知識や年代別に身につけるべき安眠スキルなどをご紹介していきます。
睡眠の主な役割
睡眠の主な役割としては「脳や身体の休養」「疲労の回復」「免疫機能の増加」「記憶の固定」「感情整理」などがあります。
深い睡眠時には成長ホルモンという物質が分泌され、タンパク質を作る働きがあるため、細胞の修復や疲労回復に効果があったり、ウイルスや細菌と戦う免疫の効果が高まるともいわれています。
さらに健康な生活を送るためには食事・運動・睡眠が大切ですが、「睡眠」は食事や運動に比べてはるかにメンタルや幸福度と深い関係があるといわれています。 睡眠が十分に取れていないとメンタルは落ち込んで、幸福度は一気に下がってしまいます。
睡眠の質は「人生の質」とも言い換えることができるほど、大切なものなのです。
【年齢別】睡眠時間の目安
睡眠は年齢とともに変化するということがわかりやすい指標の1つに「睡眠時間」があります。 ここでは年齢別で睡眠時間の目安をご紹介してきますが、これはあくまでも平均値であり、必要な睡眠時間には個人差があることが前提です。 この差について詳しく知りたい場合は、「睡眠時間の個人差について解説!【ショート・ロング・バリアブル】あなたはどのタイプ?」をご覧ください。
睡眠時間を調べた数々の論文をまとめたデータによると以下のように報告されています。
12歳までの睡眠時間この年齢までは1〜2歳頃や3歳頃から小学生に上がる前の未就学児と呼ばれる時期と小学生以上では目安が異なります。 未就学児の場合では、1~2歳頃はトータルで約11〜14時間、3歳~5歳頃は約10~13時間程必要といわれることが多く、この時期は夜間の睡眠が短い場合はお昼寝で補うなどして時間数を確保しています。 小学生以上になるとお昼寝の時間は基本的になくなるので、夜間の睡眠時間の目安は9〜11時間です。 また、赤ちゃんの時期には必要とする睡眠時間も違ってきますので、詳しくは 「赤ちゃんの眠り|幸せ脳は質の良い睡眠からつくられる」を参考になさってください。
12歳~25歳の睡眠時間中学生〜高校生、大学生など学生時代に入ると必要睡眠時間の目安は約7〜9時間になるといわれています。 生活スタイルの変化によって就寝時間が遅くなるケースが多く、朝なかなか起きられないなどといった悩みも増えてくるのが特徴です。
25~40歳の睡眠時間社会人になり、活動していく時期の睡眠時間の目安は約7〜8時間とされています。 仕事を終えて夜に好きなことをしたり、ゲームやパソコン、スマホなどの電子機器を多用したりして眠りに入るまで目まぐるしく活動していることが増えており、睡眠の質は決して良いといえない場合があります。 また、女性は33歳で大厄がありますが、多少の個人差はあれど人間は厄年のタイミングでホルモン分泌が急に低下するといわれています。 睡眠ホルモンと呼ばれている「メラトニン」も分泌量に変化が出る時期なので、適度な運動が効果的です。
40~50歳の睡眠時間年齢的にも一般的に人生の折り返しとなるこの時期は、約6〜7時間が平均的な睡眠時間です。 男性は42歳で大厄がありますが、女性同様に睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌量が下がってくるため、今まで睡眠に悩みのなかった方でも「寝ても疲れが取れにくくなった」「睡眠が悪くなった」と初めて感じるタイミングになる可能性があります。
50歳~60歳の睡眠時間この時期には必要な睡眠時間も短くなり、約6時間程度といわれています。 年を重ねると若い頃と比較して早寝早起きになる傾向があり、これは体内時計の加齢変化によるもので、睡眠だけではなく、血圧・体温・ホルモン分泌など睡眠を支える多くの生体機能リズムが前倒しになります。
年代別:安眠に必要なスキルとは?
ここでは年代別に安眠を得るために注意すべきポイントをご紹介していきます。 それぞれの年齢の特性を理解し、眠りを味方につけましょう。
20代は仮眠を効率よく利用する先ほどお伝えしたように20代は平均して約7〜9時間の睡眠時間が必要とされています。 しかし、仕事でもプライベートでもやりたいことがたくさんある時期なので、睡眠時間を削ってしまう傾向があります。 エネルギーがあふれているので、少しくらい寝る時間が短くなったとしても身体への不調や病気のリスクなどの心配はないかもしれませんが、寝不足による事故や仕事でのミスにつながる可能性は高まります。
20代の皆さんは眠気のあるときにどんな対策をしているでしょう。 カフェインやエナジードリンクに頼っている方が多いのではないでしょうか。 実は、若者の方が高齢者よりもカフェインの効果と持続力が薄いとされています。 カフェインの覚醒効果を最大限に活かすには、年を重ねてからの方が良いということになります。
20代で必要な睡眠時間よりも少ないと感じたり、日中に眠気がある場合に効果的なのは、「仮眠」です。 仮眠といっても20分を越えるものは逆効果になりますので、5〜10分程度の仮眠を何度か取ることがポイントです。
短時間の仮眠を取るのが難しいと感じるときは、5分間アイマスクなどをつけて目を閉じたり、デスクに突っ伏した状態や椅子の背もたれに寄りかかって寝るだけでも十分休まります。 音が気になるときはイヤホンをしてリラックスした音楽を掛けるのもおススメです。
うっかり寝すぎてしまわないようにアラームやバイブの設定をすることを心掛けましょう。
30代はパートナーと寝具を別々にするのが鉄則若いときはあまり気にならなかったかもしれませんが、30代はパートナーと寝具(敷き・掛けふとん)を別々に分けることを強くおススメします。 疲れが溜まりやすくなる年代なので、睡眠の質を上げて日々の活力に変えるための工夫が必要です。
実際にダブルサイズの敷き寝具で2人で寝ている場合、ダブルサイズの横幅は140㎝しかありませんので、単純に半分ずつとしても1人70㎝のスペースで寝ることになります。 日本人男性の平均肩幅は約45cm、女性は約40cmなので、寝返りをするには男女ともに肩幅の倍の幅が必要です。 男性の場合約90cm、女性の場合は肩幅80cmとなるのですが、ダブルベッドの幅では足らないことがわかります。 そこでおススメなのはシングルサイズの敷きふとんやマットレスを2つにし、1人ずつ寝床を別にする方法です。 シングルサイズは横幅が100㎝あるので、パートナーを気にせず自由に寝返りを打つことができます。 どうしても一緒に寝たいという方はクィーンサイズ(可能であればキングサイズ)以上の敷き寝具を選ばれた方が良いかと思います。
また、様々な調査結果によると寝るときの最適温度については男女で平均して約3℃の差があるそうです。 一般的に男性が女性よりも低い温度設定を好む傾向なので、夏にクーラーで冷えすぎることや冬に暖房が弱いなどと女性が感じる場面が出てくることがあります。 3℃までであれば掛けふとんで調整することが可能なので、敷き寝具に加えて掛けふとんも別々ものを用意するようにしましょう。
40代はパジャマの素材に気を使う最近は安眠する方法の1つとして「パジャマを着る」ということが少しずつ認知されているように思います。 パジャマを着るメリットを知りたい方は「パジャマの役割って何?」をご覧ください。 パジャマを着ることに加えて、さらに40代の方はもう1ポイント「素材」を気にすることを意識してみましょう。 実は年齢を重ねるにつれて肌の油分が低下していきます。 そして年齢と共に深い睡眠に入りにくくなります。 このことからパジャマの素材を意識することが睡眠の満足度に高い確率でつながるといえます。
もともとパジャマの素材は蒸れにくい天然素材の綿がおススメではありますが、40代の方はさらに肌触りを重視した高品質なコットンやオーガニックコットンなど身にまとっていてリラックスできるような素材を取り入れてみましょう。 肌に優しい素材であれば、寝ている間の摩擦で睡眠の質が下がるといったこともなくなります。 また、素材にこだわっているタオル生地のパジャマも着心地が良いものが多いです。
さらに素材の中で1番高価かと思いますが、やはりシルク生地のパジャマは格別です。 肌に近いタンパク質を持つシルクは最も肌馴染みが良いとされています。
パジャマ生地は1つの素材でも生地の織り方や厚み、伸縮性によって肌触りは違うため、可能ならお店に足を運んで触ったり、生地感を確かめてから選ぶことをおススメします。
50代はふとんにいる時間を意識的に調節する50代になると睡眠ホルモンである「メラトニン」が低下して、深い睡眠の時間が減少します。 そして必要な睡眠時間も平均すると約6時間と短くなっていきます。 体力も低下してくるので、寝る時間は長く必要ないのにふとんにいる時間が増えて「睡眠過剰」という状態になりやすくなります。 そうすると、元から多くなっていた浅い睡眠が増えてしまい、さらに睡眠が浅くなるという悪循環を招く可能性があります。 50代を境に「実際に眠れる時間」と「ふとんにいる時間」が逆転する傾向にあるのです。
これに対する身につけるべきスキルは「体力をつけて、ふとんに入る時間を意識的に減らす」ことです。 50代からの夜更かしは体力があることが大切なので、普段歩いている以上の運動やトレーニングが必要ですが、この時間調整が上手く機能すれば、自分の好きなことがやれる時間が増えるので、趣味が充実したり、新しいことへ挑戦したりと視野が広がるきっかけになります。 例えば、「夜10時に寝て、朝5時に起きる」パターンですと起床時間が早すぎる場合は、「夜11時に寝て、朝6時に起きる」、「夜12時に寝て、朝7時に起きる」といったように必要以上に早く寝ることを避けて、ふとんにいる時間を適当なものに調整していきましょう。
60代は夜間のトイレ対策を考える60代の方の約40%夜中にトイレに起きるということをご存知でしょうか。 特に男性に多いとされていますが、女性でも約20%程は夜間頻尿に悩まされているとの報告もあります。
夜中に起きるということは、睡眠が浅くなってしまったり、朝の目覚めの悪さにつながるので睡眠障害を引き起こすリスクもあります。 では夜間のトイレ対策としてどんなことに注意をすればよいでしょうか。 3つのポイントをご紹介します。
①身体をあたためる 単純に身体が冷えるとトイレに行く回数が増えます。 就寝中に体温を下げすぎないように冬は、寝る直前まで湯たんぽを入れてふとんをあたためる、腹巻きをするなども効果的です。 また、食事にショウガを取り入れるなどの工夫もおススメです。
②寝る前の水分に注意する 寝る前に水分を摂りすぎないように心掛けましょう。さらに注意したいのがアルコールやカフェインです。 60代に限らず、就寝前には摂取しない方が好ましいですが、年齢が上がるにつれて身体の中に残る時間が長くなるので60代の方は就寝の4〜5時間前までにしておくのが理想的です。
また、ふとんに入る前にトイレを必ず済ませておくことも大切です。
③塩分を控える 塩分が多いと比例して水分を摂りたくなってしまうので、注意が必要です。 食事や間食の際は塩分を意識したものを食べるようにしましょう。 1日の塩分摂取量が9.2gを超えると頻尿のリスクが上がるともいわれていますので、意識して控えめにすることが重要です。
また、夜間頻尿の原因は夜間の尿の量が増える『夜間多尿』、膀胱にうまく尿がためられなくなる『蓄尿障害』などの要因が重なって発生している場合もありますので、上記を試してみて改善しないようでしたら専門機関を受診されることをおススメします。
こんなときはどうする?お悩み別の対策方法
年齢を重ねるにつれて、睡眠についての悩みも変化していくものです。 今回はいくつかの事例に対しての対策方法を解説していきます。 ぜひ参考になさってください。
年を重ねていびきがひどくなった若い頃はいびきと無縁だったのに、30代後半から「いびきがうるさい」といわれることが多くなるのが一般的です。 いびきが大きくなる原因の1つに若い頃に比べて代謝が落ちることや運動不足などでの肥満がありますが、老化によって舌が垂れて気道を塞いでしまうこともあります。 ここでは2つの対策をご紹介していきます。
【枕の見直しと横向き寝】 自分に最適な高さや素材の枕に変えてみるのも有効ないびき対策になります。 仰向けに寝ると重力の影響で気道がふさがりやすくなってしまうので、体を横向きにし、体位を変えることで気道を確保する方法を1度試してみてください。 また、効果が期待できる方法のひとつに、抱き枕を使う方法があります。 横向きでの睡眠をサポートすることができて、舌根沈下を防げるため、いびき防止につながります。
【いびき防止グッズを試す】 顎の骨格や形状に合わせたマウスピースを使用すると寝ている間に舌が下がることを防ぎ、気道を確保し、いびきをかきにくくなります。 顎が小さいことが原因でいびきをかいてしまう方や首回りの筋肉の衰えによりいびきをかく方におススメの対策です。 ドラッグストアなどで購入できるものもありますが、自身の骨格に合っていることが望ましいので、専門機関を受診してオリジナルのマウスピースをつくる方が効果は高まります。
鼻腔拡張テープは鼻づまりが原因でいびきをかいてしまう鼻いびきの方におススメです。 貼ることで鼻の通りが良くなり鼻呼吸がしやすくなります。 口に貼るテープは鼻づまりがないのに口呼吸をしてしまう口いびきの方におススメです。 テープで口を閉じることにより自然な鼻呼吸ができて、いびきがかきにくくなります。 鼻呼吸を意識し、習慣化させることもいびき改善に有効です。
子どもが生まれて睡眠の質が下がった新生児(生後1〜2ヶ月)は昼夜の区別なく2〜3時間の短い眠りと授乳を繰り返し、1日におよそ14〜18時間の睡眠をとるといわれています。 お世話をするお父さんやお母さんにとっては、睡眠時間がこま切れになりがちで大変な時期ですが、これはまだ睡眠覚醒リズムが確立していないため、赤ちゃんの眠りのメカニズム上、致し方ないことなのです。
この時期は過ぎて、夜間にまとめて寝るようになったけれど何だか睡眠の質が悪い・・・と感じてる方は一緒に並んで寝る順番を変えてみましょう。 基本的に「川の字」で寝ることはやめて、お父さん・お母さん・お子さんの順に横並びになるようにしてみることがおススメです。 さらにお母さんとお子さんの間に抱き枕を置くのも効果的です。 実は親子で寝ると男性の方が睡眠の質が下がりやすいのが一般的といわれています。 睡眠不足や質の低下に伴い、男性ホルモンも低下するので仕事のパフォーマンスが下がってしまう可能性があります。
同じ部屋でも寝るときの位置を変更することで改善が期待できます。 また、可能であれば全員別々のふとん(敷き・掛け)で眠ることが好ましいです。
アルコールを飲んだときに眠りが浅くなるアルコールを飲むとリラックスして、眠りに入りやすくなりますが、途中で起きてしまったり、トイレに行く回数が増えたりとデメリットも多くなります。
アルコールを摂取する際は出来れば21時までにするのが望ましいですが、アルコールを飲む前にトマトジュースを飲むとアルコールの分解が促進されるので、そこまで眠りが浅くならずに済むかと思います。 また、アルコールと同時に水(チェイサー)を用意して交互に飲んだり、アルコールを飲んだ後にはイオン飲料(薄めのスポーツドリンク)を飲むと体内のアルコール濃度を下げることができるので眠りが浅くなると感じる方へはおススメの対策です。
まとめ
人間は生まれてからとてもたくさんの時間を睡眠に費やします。 年齢によって変化する睡眠の特徴や知識を理解して上手に工夫を重ねていくことで睡眠の質は確実に上がっていきます。 今日の眠りは明日の元気につながっています。 眠りを潤わせて、明日への活力へと変えていきましょう。 |
|
関連記事 |
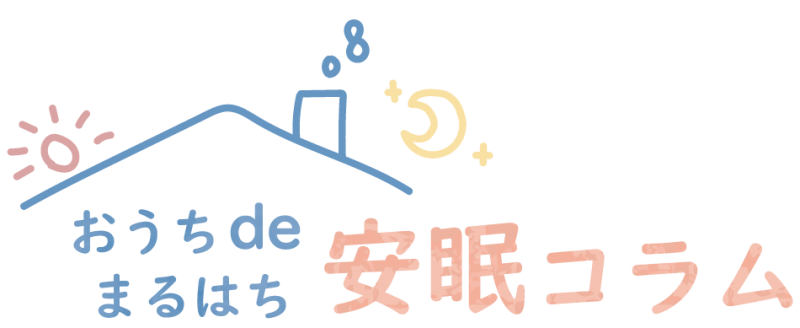 寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載
寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載
新着記事