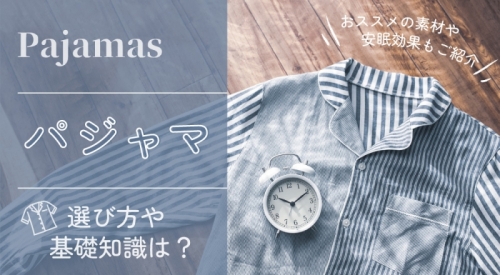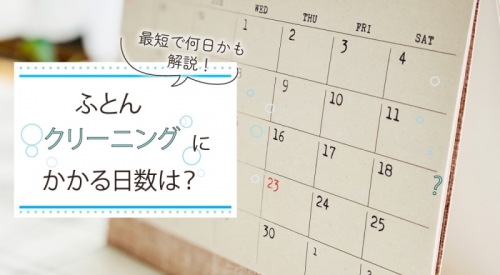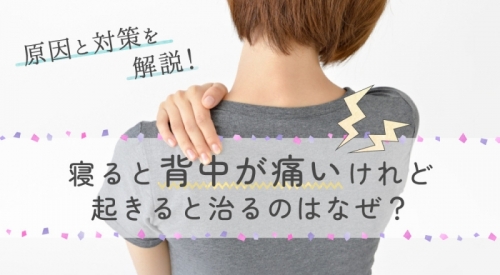なぜ朝起きられない?原因は生活リズムと睡眠の質にアリ!?
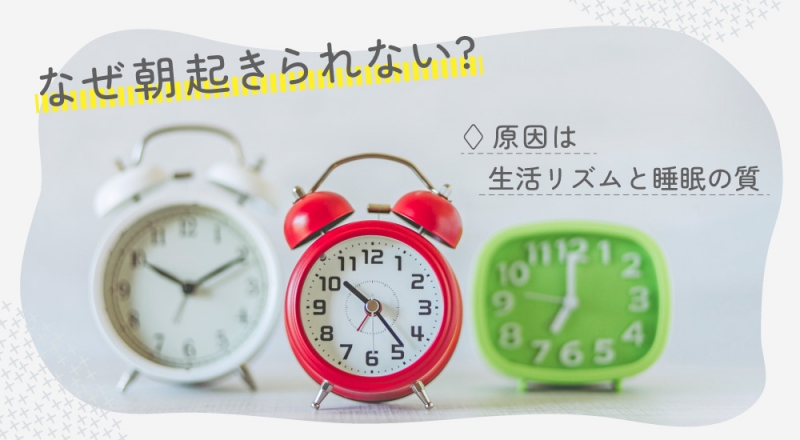
|
「きちんと寝ているはずなのに朝スッキリ目覚められない」 「どうしても朝起きるのが苦痛」 「また朝起きられなかった」
学校や仕事があるのに、朝起きられないと悩んでいる方もいるでしょう。
朝起きられない原因は、日ごろのストレスや寝る直前の習慣などさまざまです。 しかしそのままにしていると、身体にどんどん疲れがたまり、大きな病気へつながる恐れがあります。
ここでは朝起きられない原因や解消方法についてご説明します。 生活リズムを整える方法や質のよい睡眠を得る環境づくりや寝具についても詳しく解説。 ぜひ健康的で快適な毎日を送るための参考にしてください。 |
朝起きられない原因とは?
1日が始まる朝。 どうしてもスッキリ起きられないと困っている方もいるでしょう。 中には起きられなくて、学校や仕事に支障をきたしているケースもあるのではないでしょうか?
朝起きられない原因はさまざまです。 原因が1つの場合もあれば、複数の要因が入り混じっている可能性もあります。 ここでは朝起きられない、代表的な原因についてご説明します。
睡眠不足朝起きられない原因の1つは「睡眠不足」です。 寝入る時間が遅いと目覚ましを鳴らしても起きられないことがあります。
では、どれくらい睡眠時間を確保できればよいのでしょうか? 個人差はありますが、成人の80~90%の方が該当するバリアブルスリーパーの場合、理想の睡眠時間は6~9時間といわれています。 バリアブルスリーパーとは、睡眠時間を削ったり延ばしたりと変化させられる特徴を持っており、上記の時間より短い睡眠時間しか取れない状態が長く続くと、睡眠不足症候群になる可能性があります。
自分にとって理想的な睡眠時間をしっかり確保しましょう。 睡眠時間の個人差については、こちらの「睡眠時間の個人差について解説!【ショート・ロング・バリアブル】あなたはどのタイプ?」をご覧ください。
睡眠不足症候群は日中の眠気だけでなく、頭痛・めまい・吐き気・血圧の上昇など身体的なものから、集中力の低下や気分が落ち込む・イライラしやすいなどの精神的な症状も出現します。
仕事のミスが増えたり、交通事故の原因となったりと生活に出る影響は非常に大きいです。 また心臓病や脳卒中・糖尿病・高血圧など、さまざまな病気にもつながります。
忙しくて睡眠時間をなかなか取れない方もいると思いますが、なるべく6時間以上の睡眠を確保しましょう。
睡眠相後退症候群(すいみんそうこうたいしょうこうぐん)睡眠相後退症候群は午前3~6時ごろの朝方にしか入眠できず、昼ごろまたは昼過ぎにならないと起きられなくなるものです。
人間はいつもだいたい同じ時間に眠くなり、同じ時刻に起床します。 これは体内時計がおおよそ24時間10分の周期で働いているからです。 通常は夜眠くなり朝に起きるよう体内時計が動いていますが、夜遅くまでゲームやスマホをしていたり、活動していたりすると体内時計のリズムがどんどん後退します。
重要な用事があるのにもかかわらず朝に起きられないため、社会的不利益をこうむることが多いです。
閉塞性睡眠時無呼吸症候群(へいそくせいすいみんじむこきゅうしょうこうぐん)閉塞性睡眠時無呼吸症候群は、肥満や下あごが小さい・扁桃腺肥大などによって上気道が狭まることで生じる疾患です。 睡眠中に息が止まったり、低呼吸となったりすることで酸欠状態となります。 すると深い眠りが得られないため、睡眠時間は十分なのに熟睡感が得られなくなったり、寝起きが悪くなったりします。
大きないびきをかいている、短時間呼吸が止まっているなどと指摘されたことのある方は要注意です。 心配な方は一度専門の医療機関を受診してみるとよいでしょう。
低血圧低血圧も朝起きられない原因の1つです。 だいたい収縮期血圧が100mmHgを下回ると低血圧と呼ばれます。
血圧が低いと体内をめぐる血流量が減るため、脳が酸欠状態に。 すると起床時間になっても脳が目覚めにくくなり、身体全体の目覚めも悪くなります。
貧血になっている方はさらに症状が悪化するため、注意してください。
起立性調節障害起立性調節障害とは、自律神経の働きが悪くなり、立ったときに全身をめぐる血流が低下する病気です。 朝なかなか起きられなかったり、立ちくらみ・めまい・頭痛・全身倦怠感などの症状が出現したりします。
この病気の特徴は午前中の調子がもっとも悪く、午後になると症状が改善することです。 思春期に発症することが多く、不登校の原因にもなります。
ストレスストレスがある状態で眠ると、緊張状態が続くため深い睡眠を得にくくなります。 また寝つきが悪くなる、途中で目が覚めるなどの症状が現れます。
仕事や人間関係・将来への不安など、誰しもがストレスを抱えている現代。 誰かに話を聞いてもらったり、自分の時間を作ったりなどして、リフレッシュできる環境を作れるとよいでしょう。
なるべくストレスはふとん内へは持ち込まず、考え事は朝にするようにしてください。
うつ病うつ病と聞くと寝られなくなるイメージがありますが、過眠を生じるケースもあります。 特に若い女性に多く見られる「非定型うつ病」の特徴的な症状の一つに過眠があります。
従来のうつ病は落ち込んでいる状態がずっと続きますが、非定型うつ病は好きなことや楽しいことをしている間は元気です。 また夕方に症状が強くなる点も、朝方に症状が強い従来のうつ病と異なっています。 うつ病かもしれないと感じたら、早めに精神科や心療内科を受診しましょう。
生活リズムを整えて朝起きられるように!
スッキリと朝起きられるようにするために1番大切なことは、生活リズムを整えることです。 ここからは、生活リズムを整えるポイントについてご説明します。
朝日を浴びる私たちの体内時計は24時間ちょうどではなく、少し長めに設定されています。 そのままにしておくとだんだんずれてしまうのですが、朝日を浴びることでリセットできます。
朝起きたらカーテンを開け、しっかり朝日を浴びましょう。 夜の快眠につながります。
また冬は日照時間が短く、起床時間になっても朝日が昇っていないことがあります。 雨やくもりなど、天気の悪い日も同様に朝日を浴びるのは難しく、朝起きづらいと感じることがあるでしょう。 その場合は照明をうまく活用するとよいです。
1日3回食事をとる食事は1日3食しっかり取りましょう。 特に朝食を疎かにしがちですが、少量でもよいので毎日食べるようにしてください。 時間のない方はスープや野菜ジュースなどでもよいです。
お腹に物を入れることで内臓が刺激され、身体が目覚めます。 さらに朝食をとることが体内時計のスイッチを入れることにもつながります。
夕食は基本的に寝る3時間前までに取るようにしましょう。 どうしても時間がなく、寝る直前にしか食事が取れない場合は消化がよい炭水化物などを少量にしてください。 興奮作用のあるカフェインの摂取は寝る4時間前までにするとよいでしょう。
運動する習慣を作る頭は疲れていても、身体が疲れていないとなかなか寝られないこともあります。 適度に汗ばむ程度の運動をすると寝つきがよくなります。
ただし一度だけの運動では、あまり効果は得られません。 習慣にすることが大切です。
夕方から夜に行うとより効果的です。 夕方~19時ごろに行うとよいでしょう。
あまり激しい運動をすると、逆に興奮して寝られなくなってしまうため、散歩やジョギング・ヨガなどがおススメです。
同じ時間に起きるなるべく同じ時間に起きるようにしましょう。 脳は朝、太陽の刺激を受けると一定時間後に眠くなる仕組みになっています。 つまり朝の時間をそろえれば、夜に寝る時間もそろえられます。
休日に寝溜めをする方もいると思いますが、なるべく同じ時間に起きるようにしてください。 平日と休日の起床時間の差は、2時間以内におさめるようにしましょう。
就寝1時間前になったらスマホを触らない寝る直前までスマホを触っている方も多いでしょう。 しかしスマホやテレビの画面から発せられる明るい光を夜に浴びると、脳が昼間であると誤認してしまいます。 その結果、脳が活性化されて寝つきが悪くなったり、睡眠が浅くなったりしてしまいます。
就寝時間の1時間前になったら、スマホやテレビをシャットアウトしましょう。
寝る前に入浴をして身体を温める寝る1~2時間前に身体を温めると、快眠効果が得られます。
人は体温が下がると眠気が誘発されます。 お風呂に入ることで体内温度が一時的に上昇。 就寝の1~2時間前にお風呂に入れば、ちょうどふとんに入るタイミングで体温が下がってくるため寝つきがよくなります。
ただし42℃以上の熱いお湯に浸かると、交感神経が活性化されて眠りにくくなるため注意してください。 もっともよい湯温と入浴時間は38~40℃、20~30分になります。
朝起きられるように睡眠の質を上げる
朝スッキリ目覚めるためには、睡眠時間だけでなく睡眠の質も大切です。 睡眠の質は、寝る環境や使用する寝具などの影響を受けます。
どのように周囲の環境を整えればよいのか、順番にみていきましょう。
寝室の環境を整える心地よい眠りを得るために、静かでリラックスできる空間にしましょう。 部屋のレイアウトやベッドの大きさなど、すぐに対処できないものもありますが、照明の明るさや湿温度・キレイな空気などすぐに改善できることもたくさんあります。
快眠が得られる寝室環境について詳しく知りたい方は「ぐっすり眠れる寝室環境|どんなことに気を配ればいい?簡単実践5つの角度からアドバイス!」をご覧ください。
また、朝スッキリ起きられるように環境を整えることも大切。
次のポイントに注目して、環境を整えてください。 • カーテンを少し開けておく • 目覚まし時計の音は柔らかい音にする • 冬は暖房をタイマーでセットしておく
カーテンを少し開けておけば、太陽が昇るタイミングに合わせて部屋が徐々に明るくなります。 起床時刻に部屋が明るいと起きたときの眠気や疲労感が少なくなり、スッキリ起きられます。 特に光を遮る遮光カーテンを利用している方は、朝方も部屋が暗いままになるため、カーテンを少し開けて光を取り込むようにしましょう。
朝「ジリリリ」と大きく強い音を目覚ましにセットしている方も多いのではないでしょうか? びっくりして起きられるかもしれませんが、一気に交感神経が優位になるため血圧が上がり、疲労感や不快感が強くなります。
心地よい目覚めを得たい方は、徐々に音量が上がるタイプやクラシックなど柔らかな音が鳴るように目覚ましをセットしましょう。 アラームは2段階での設定がおススメです。 1回目はごく微音で短くし、2回目は20分後に設定します。 浅い眠りであるレム睡眠のときに刺激が与えられる可能性が高まり、覚醒しやすくなります。
寒くてふとんから出られなくなる冬は、起きる30分くらい前から部屋を温めておきましょう。 エアコンのタイマー機能を使うとよいです。 暖房を使用すると乾燥するため、加湿器も同時に使用できるとさらに快適に目覚められます。
身体にあった寝具を使用するどのような寝具を使用するかも、睡眠の質を左右する大きな要因です。 睡眠中には寝返りや発汗・体温低下などさまざまな生理的変化が生じます。 これらの生理的変化を妨げず、快適な環境を維持できるかが安眠のポイントです。
ふとんのフィット性や重さに加え、保温性・吸放湿性に優れた最適な寝床内気候条件が維持できるものを選びましょう。
寝床内気候条件とは、寝ている間のふとん内の湿度や温度のことです。 理想的な寝床内気候条件は「温度33±1℃」「湿度50±5%」といわれています。 季節に合わせて、心地よいと感じられる環境を維持できる寝具を選びましょう。
ふとんを清潔に保ちよい睡眠へ最適な寝具選びも大切ですが、寝具の機能を最大限引き出すために清潔に保つこともとても重要です。 汚れたままの寝具を使用していると、保温性や吸放湿性が低下することがあります。 またダニやカビ・雑菌の温床となる可能性も。
ダニやほこりはアレルギーを引き起こす原因ともなり、人体に影響を及ぼします。
心地よく安心して寝られるように、ふとんを清潔に保ちましょう。
ふとんを清潔に保つためには、日々のメンテナンスも大切ですが定期的なクリーニングも欠かせません。 ふとんクリーニングについて詳しく知りたい方は「【ふとんクリーニング】業者に依頼すべき7つのワケ|頻度・タイミングは?」もご覧ください。
まとめ
朝に起きられるようにするためには、生活リズムを整え、睡眠の質を上げることが重要です。 少し意識を変えるだけで、快適な朝を迎えられるようになるかもしれません。
ぜひ実践してみてください。
また快眠に欠かせない寝具は身体にフィットし、保温性・吸放湿性の優れたものを選びましょう。 そして寝具を快適に使い続けるため、清潔に保てるようにしてください。
そのために定期的なふとんクリーニングを行いましょう。 ふとんクリーニングをどの業者にお願いしようか迷っている方は、ぜひ一度「おうちdeまるはち」にご相談ください。
朝起きられない原因はさまざまです。 中には治療の必要な病気が隠れていることもあります。 不安な方は一度、専門の医療機関で診てもらいましょう。 |
関連記事
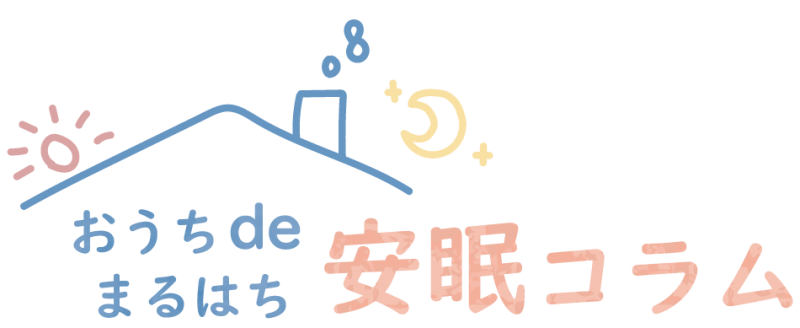 寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載
寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載
新着記事