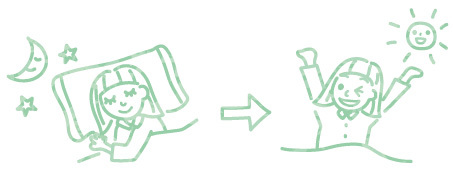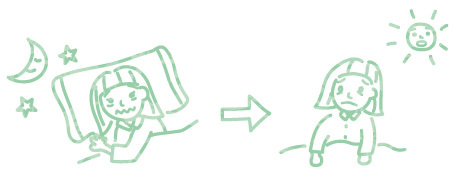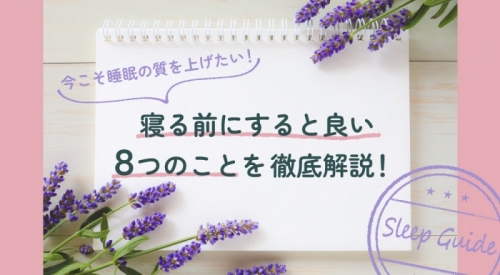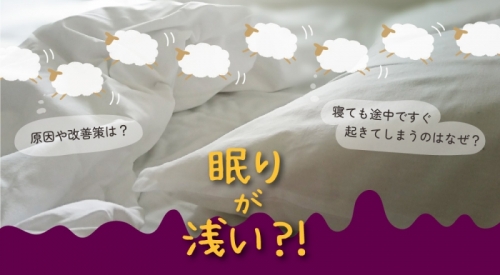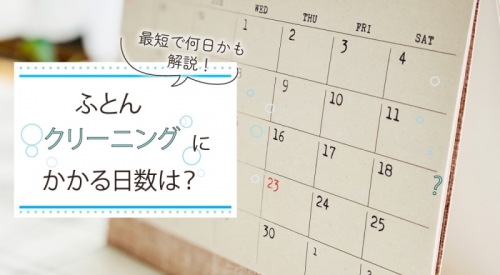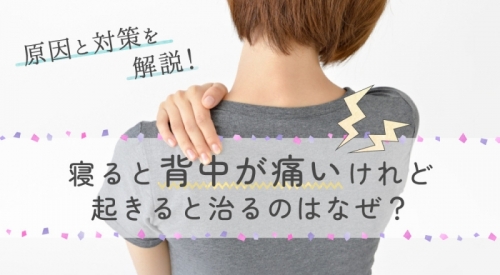睡眠のメリットと睡眠不足のデメリットとは? 重要性を理解し自分にあった快眠法を探そう
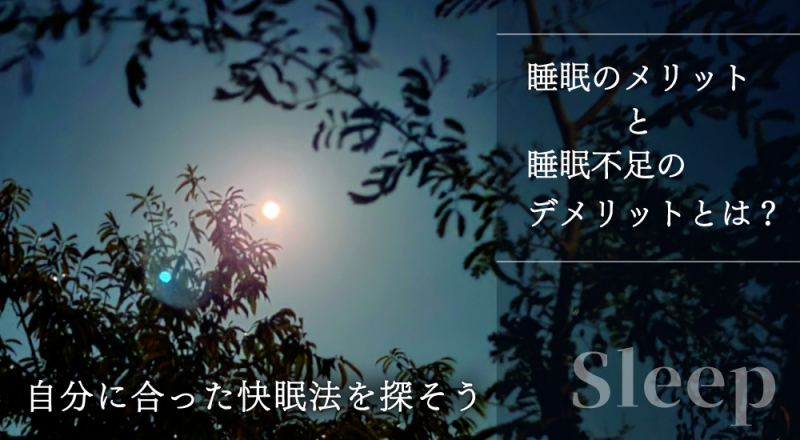
|
|
執筆者情報:軽石 瑞穂 【業務内容】 おうちdeまるはちWEB関連運用 |
| 長年ふとんクリーニングや寝具のメンテナンスに携わり、お客様の快適な睡眠環境をサポートしてきました。安眠インストラクターや快眠セラピストなど睡眠に関する専門知識を活かし、ふとんクリーニングの重要性や家庭でできる快眠のヒントなど皆様の睡眠の質を向上させる為の情報をお届けします。 |
健康な生活には食事・運動・睡眠が不可欠ですが、実は睡眠は、食事や運動以上に私たちのメンタルや幸福度と深く結びついています。
睡眠が不足すれば、気分は落ち込み、人生の満足度は一気に下がってしまいます。
このことから、「睡眠の質は人生の質に繋がる」と考えられます。
また睡眠は単なる休息ではなく、「脳や身体のメンテナンス」「疲労回復」「免疫力の強化」「記憶の固定」「感情の整理」といった、私たちが最高のパフォーマンスを発揮するために欠かせない多くの役割を担っています。
この記事では睡眠科学の観点からメリット・デメリットを徹底解説し、あなたの睡眠を改善するポイントから具体的な実践法まで、幅広くご紹介します。
この記事を読んでわかること●睡眠がもたらす5つのメリット ●睡眠不足が招く4つのデメリット ●睡眠の質を高める3つのポイント |
睡眠が担う4つの重要な役割
そもそも、なぜ睡眠はこれほど重要なのでしょうか。
「健康」という言葉は、もともと「健体康心(けんたいこうしん)」という四字熟語からきています。 つまり、身体が健やかで、心が康(やす)らかであってこそ、真の健康といえるのです。
睡眠は、この「身体」と「心」の両軸に、以下のような極めて重要な働きをしています。
【身体への役割】 ・身体の休養と疲労回復: 全身の細胞を修復し、日中の活動で蓄積した疲労物質を分解します。 ・免疫機能の強化: 免疫細胞を活性化させ、ウイルスや細菌への抵抗力を高めます。
【心(脳)への役割】 ・記憶の整理と定着: 日中に得た膨大な情報を整理し、必要な知識を長期記憶として脳に刻み込みます。 ・感情の整理とストレス軽減: 嫌な記憶やストレスを和らげ、精神的な安定をもたらします。
これらの役割を理解した上で、まずは睡眠がもたらす素晴らしい「メリット」から見ていきましょう。
知っておきたい、睡眠がもたらす5つのメリット
質の高い睡眠を確保することは、私たちの生活に多くの恩恵をもたらします。
①心身の疲労回復睡眠には、心身の疲労を回復させる重要な役割があります。 深い眠りは脳をクールダウンさせ、ストレスからの回復を助けます。 自覚がない部分も含めて全身をメンテナンスしてくれるため、翌朝には心身がリセットされたような爽快感が得られます。
②成長ホルモンの分泌促進睡眠中、特に寝入りばなの深いノンレム睡眠時に、成長ホルモンが大量に分泌されます。 このホルモンは子供の成長だけでなく、大人の私たちにとっても細胞の修復、代謝の促進、疲労回復に不可欠です。
③記憶力と学習能力の向上睡眠は、脳の情報を整理し、記憶を定着させるための重要な時間です。
・深いノンレム睡眠・・・新しい知識やスキルを脳に刻み込む ・レム睡眠・・・既存の記憶と新しい情報を結びつけ、応用力を高める ・浅いノンレム睡眠・・・スポーツの技術など、身体で覚える記憶を定着させる
睡眠の全ての段階が、学習効率を最大化するために必要なのです。
【深掘り】脳のゴミを洗い流す!?「グリンパティックシステム」 近年の研究で、深い睡眠中に脳内の老廃物(アミロイドβなど)が洗い流される「グリンパティックシステム」という脳の自浄作用が発見されました。 この老廃物の蓄積はアルツハイマー病の一因とも考えられており、質の高い睡眠が将来の認知症予防にも繋がる可能性が示唆されています。※1
④免疫力を高め病気を予防十分な睡眠は、免疫システムを正常に機能させ、風邪やインフルエンザなどの感染症への抵抗力を高めます。 逆に睡眠不足はホルモンバランスを乱し、免疫機能を低下させるため、「寝ないと病気にかかりやすくなる」というのは科学的な事実です。
⑤美肌・アンチエイジング効果美肌を保つためにも睡眠は欠かせません。 睡眠中に分泌される成長ホルモンが肌のターンオーバー(新陳代謝)を促進し、日中に受けた紫外線などのダメージを修復します。 また、コラーゲン生成も活発になり、肌の弾力やハリを保ち、シワやたるみの予防にも繋がります。
放置は危険!睡眠不足が引き起こす深刻なデメリット
「睡眠負債」という言葉の通り、睡眠不足は着実に心身を蝕んでいきます。
①生活習慣病(糖尿病・高血圧)のリスク増大睡眠不足はホルモンバランスを崩し、血糖値のコントロールを乱したり、血圧を上昇させたりします。 厚生労働省の「e-ヘルスネット」でも、睡眠不足が糖尿病や高血圧などの生活習慣病のリスクを高めることが指摘されています※2。 慢性的な睡眠不足が、将来的に健康を損なう一因となる可能性があります。
②集中力や作業効率の劇的な低下睡眠不足は人間の精神と体に悪影響を与え、判断力や注意力が著しく低下し、ミスの可能性を高めます。 脳が情報を整理する休息時間を奪われるため、集中力は散漫になり、普段なら簡単にできる作業にも時間がかかってしまうのです。※3
③慢性的な倦怠感や頭痛身体のエネルギーが十分に補充されず、疲労が蓄積することで、常に身体が重く、だるい状態が続きます。 また、血流の悪化から頭痛を引き起こすことも。 この状態が慢性化すると、日常生活の質そのものが大きく損なわれます。
④メンタル不調とストレス増加睡眠不足は、ストレスホルモン「コルチゾール」の分泌を促し、イライラや不安感を増幅させます。 小さなことにも過剰に反応してしまい、人間関係のトラブルに発展することも。 この悪循環は、うつ病や不安障害といった深刻なメンタル不調の引き金にもなり得ます。
眠りに関する新常識「3つのポイント」
デメリットを理解したところで、次は改善への第一歩です。 しかしその前に、あなたの睡眠に関する古い常識をアップデートする必要があります。
ポイント①:「寝ずに努力」から「寝るために努力する」「睡眠時間を削って頑張る」という価値観は、見直されつつあります。 パフォーマンスが低下した状態で頑張っても成果は出ません。 むしろ、最高のコンディションで日中を過ごすために「質の高い睡眠を確保するための努力」こそが、現代のビジネスパーソンや学生に求められる新しい常識です。
ポイント②:「早寝早起き」ではなく「早起き早寝」から始める「早く寝よう」と意気込んでも、眠れずに焦るだけ。 実は、生活リズムを整えるコツは「早起き」が先です※4。 いつもより15分早く起きるだけで、夜には自然な眠気が訪れやすくなります。
これを続けることで、「早起き→早寝」という理想的なサイクルが生まれるのです。
ポイント③:「夜の楽しみ」を「朝の楽しみ」へシフトする「好きなことは夜にしかできない」と思っていませんか? しかし、疲弊した夜の脳では、趣味も心から楽しめません。
私自身、以前は「夜更かししてでも好きなことをする」のが唯一の楽しみでした。 しかし、朝の倦怠感と日中の集中力散漫に悩み、思い切って「朝活」に切り替えたのです。 最初は早起きが辛かったものの、1週間もすると驚くほど日中のパフォーマンスが上がり、夜は自然と眠くなるという好循環が生まれました。 リフレッシュした朝の脳で好きなことをする方が、同じ時間でも数倍楽しめますのでおすすめです。
睡眠の質を劇的に高める3つの方法
意識が変われば、次はいよいよ行動です。 ここでは、睡眠の質を高めるための3つの方法をご紹介します。
①運動|夕方のウォーキングと寝る前のストレッチ人間は、深部体温(身体の内部の温度)が下がるタイミングで眠気が訪れます。
運動で一時的に体温を上げておくと、その後の体温低下との落差が大きくなり、スムーズな入眠に繋がります。
●時間帯: 夕方から就寝3時間前までが、運動に特に適した時間帯です。 ●おすすめの運動: 30分程度のウォーキングや軽いジョギングを習慣にしましょう。 ●寝る直前: 激しい運動は避け、リラックス効果のあるヨガや手首・足首、肩甲骨周りをほぐす軽いストレッチが効果的です。
②食事|睡眠を妨げない食事のコツ寝る前に何を食べるか、飲まないかは、睡眠の質に直結します。
【避けるべきもの】 刺激物(香辛料、ニンニクなど): 胃に負担をかけ、眠りを浅くします。 カフェイン: 覚醒作用があるため、夕食後以降は麦茶やハーブティーに切り替えましょう。 チョコレートや栄養ドリンクにも注意。 アルコール: 寝酒は眠りを浅くし、夜中に目が覚める原因になるので、晩酌は適量に。
【夕食のポイント】 ●揚げ物や脂っこいメニューは消化に時間がかかるため、昼食に。 ●腹八分目を心掛け、胃に負担をかけないようにしましょう。
安眠と食事の関係についてもっと詳しく知りたい方は「眠りと食事の話し|安眠をサポートする栄養素と食材とは?」をご覧ください。
③環境|寝室の「光・空気・寝具」を整える快適な寝室環境は、質の高い睡眠の土台です。
【光】 寝室は暖色系の間接照明で、リラックスできる明るさに。就寝時は真っ暗(4ルクス以下)が理想です。 逆に朝は2,500ルクス以上の強い光を浴びると、体内時計がリセットされスムーズに目覚められます。
【空気】 寝室の空気は意外と汚れています。 日中は窓を開けて換気し、空気清浄機を活用するのも良いでしょう。 ホコリが溜まりやすいカーテンは定期的に洗濯を。
【寝具】 理想的な布団の中の環境は「温度33±1℃、湿度50±5%」と言われます※5。 季節に合わせて、保温性・吸放湿性に優れた寝具を選び、快適な環境を保ちましょう。
快眠が得られる寝室環境について詳しく知りたい方は「ぐっすり眠れる寝室環境|どんなことに気を配ればいい?簡単実践5つの角度からアドバイス!」をご覧ください。
今日からできる!簡単快眠テクニック
最後に、ふとんの中でも実践できる簡単な快眠法をご紹介します。
①自分だけの「入眠儀式」をつくる寝る前にいつも同じ行動(ルーティン)をすることで、脳に「これから寝る時間だ」と知らせるスイッチになります。 (例:パジャマに着替える、ハーブティーを飲む、好きな香りを嗅ぐ、軽いストレッチをする) 自分が最もリラックスできる習慣を見つけ、入眠儀式にしてみましょう。
②1分でできる「安眠体操」ふとんの中で仰向けになり、身体の緊張をほぐす簡単な体操です。
【ステップ1】 仰向けになり、顔、手、足、全身にギュッと力を入れ、5秒間キープします。手はグー、足はつま先を上に向けます。
【ステップ2】 5秒経ったら、息を「はぁー」と吐きながら、一気に全身の力を抜いて脱力します。
これを3〜5回繰り返すだけで、血流が良くなり、自然な眠気が訪れます。
③1日の終わりを「感謝」で締めくくる寝る前に、その日にあった「良かったこと」「感謝したいこと」を1つだけ思い出してみましょう。 日記に書いても、頭の中で思うだけでも構いません。 1日をポジティブな気分で締めくくることで、不安や心配事を寝床に持ち込まずに済みます。
まとめ:最高の睡眠で、最高の明日を手に入れよう
眠っている間の記憶はなく、誰かと共有することもできないため、睡眠時間を「無駄な時間」と捉えてしまう人もいるかもしれません。
しかし、この記事で見てきたように、睡眠に配慮することは、心身の健康を維持し、より良い人生を送るための大切な要素です。 今日から睡眠との向き合い方を変え、最高の睡眠で、最高の明日を手に入れてみませんか。
参照元※1:日本脳科学関連学会連合:「脳内の老廃物排除の仕組み:グリンパティックシステム」 https://www.brainscience-union.jp/trivia/trivia4349 ※2:厚生労働省:「睡眠と生活習慣病との深い関係」 https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/heart/k-02-008.html ※3:厚生労働省:「健やかな眠りの意義」 https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/heart/k-01-001 ※4:厚生労働省:起床後に朝日の強い光を浴びることで体内時計はリセットされ睡眠・覚醒リズムが整い、脳の覚醒度は上昇します https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf ※5:厚生労働省:「よく眠るために必要な寝具の条件と寝相・寝返りとの関係」 https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/heart/k-01-003
|
関連記事
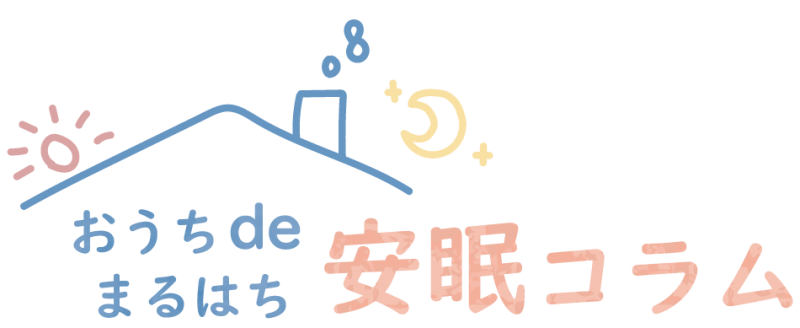 寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載
寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載
新着記事