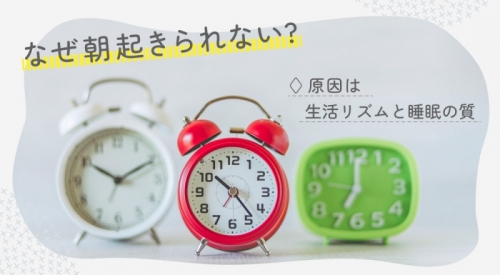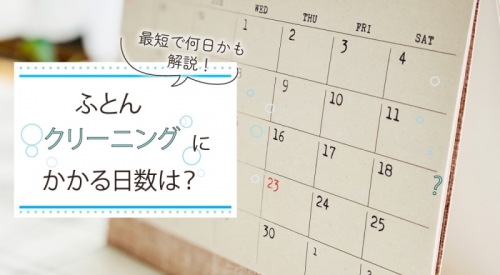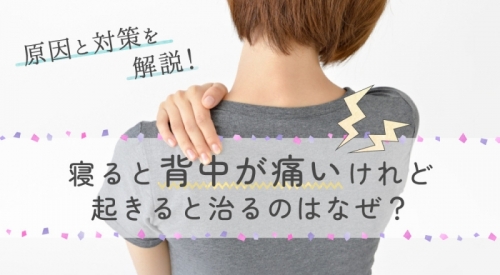眠りと食事の話し|安眠をサポートする栄養素と食材とは?

|
|
執筆者情報:軽石 瑞穂 【業務内容】 おうちdeまるはちWEB関連運用 |
| 長年ふとんクリーニングや寝具のメンテナンスに携わり、お客様の快適な睡眠環境をサポートしてきました。安眠インストラクターや快眠セラピストなど睡眠に関する専門知識を活かし、ふとんクリーニングの重要性や家庭でできる快眠のヒントなど皆様の睡眠の質を向上させる為の情報をお届けします。 |
新年度が始まり、気温も上昇して過ごしやすい季節になりましたね。
実はこの時期は新しい環境や生活リズムの変化で睡眠にも影響を及ぼしやすい傾向があります。
皆さんは最近こんなお悩みありませんか?
・朝スッキリ目覚められない
・眠りが浅い気がする
・なかなか寝付けない
睡眠の質を高めるためには、衣食住のどの角度からもアプローチを試みることができます。
例えばパジャマや寝具を見直してみたり、寝室環境を変えてみたり・・・
また、食事で身体の内側から整えてあげることもとても重要です。
毎日忙しいからといって朝食を抜いていたり、偏った食生活を続けていると健康面だけでなく、睡眠の質も落とすことになりかねません。
規則正しい食事の習慣は規則正しい生体リズムをつくり出します。
今回は眠りと食事の関係を意識して、注目したい食材や食事のコツなどをご紹介していきます。
眠りと食事の関係 |
食事のタイミングで注意したいこと

朝起きてから1〜2時間以内に朝食を食べることで体内時計がリセットされるので、必ず朝食を食べるように習慣をつけましょう。
忙しい場合は、バナナ+牛乳などの簡単なメニューでもOKです。
食べ物が胃にとどまって消化される時間は通常約2〜3時間、肉類や揚げ物など脂肪が多い食べ物になると約4〜5時間必要だといわれてます。
食べ物を消化する時間を考慮すると、食事の間隔は4〜5時間空けるのが適切です。
昼食を12時頃に食べる場合は、朝食は7〜8時頃に摂るのが望ましいといえるでしょう。
また、胃腸が盛んに働いている間は深く眠れないので、夕食の後3時間ほどあけてから眠るようにしましょう。
そのころには消化も一段落して、眠りやすくなります。
夜遅くまで仕事をしていて、夕食が眠る直前になってしまう場合は、「分食」がおススメです。
夕方〜19時頃に1回、おにぎりやパンを少し食べて、夜はスープなどの消化のよい軽めの食事を摂って深夜の食事量を減らす方法です。
こうすると胃の負担を軽減させて、翌朝の胃もたれも軽くなります。
食事をする際に覚えておきたい3つのコツ

人間は眠る前にメラトニンが分泌されて、身体と神経が徐々に休まっていくことで、健やかな睡眠を得ることができます。
「休まらない状態」にしてしまうことを避けて、睡眠を妨げない食事を意識することはとても重要です。
もし無意識に睡眠の質を下げる行動をしてしまっている場合は、次の3つのコツを実践してみてください。
夕食以降の刺激物は要注意
香辛料や刺激の強いもの:唐辛子やスパイスなどの辛いものは、胃に刺激を与えてしまうので睡眠の質の低下につながる恐れがあります。
また辛いものだけでなく、ニンニクやネギなども刺激が強いので、眠る3時間前までにして過剰な摂取は控えましょう。
カフェイン:コーヒーに多く含まれる興奮作用があるカフェインは、通常2時間程度、高齢者では4〜5時間以上身体の中に残るといわれています。
夕食後に飲むものをノンカフェインの麦茶やハーブティーに替える工夫をしましょう。
またチョコートやココア、栄養ドリンクの一部にもカフェインが含まれているので、要注意です。
アルコール:お酒を飲むと良く眠れる…という方は注意が必要です。
アルコールは睡眠中の尿の量を増やします。
そのため、トイレに行きたくなって目が覚めやすく、睡眠がこま切れになってしまいます。
夕食時の晩酌は日本酒1合、ビール(500mL)1缶、ワインはグラス2杯までを適量とし、寝酒としてアルコールを摂取するのはやめましょう。
胃に負担がかかるメニューは昼食に
揚げ物や油っぽいもの:食べた後にすぐ消化されるものは良いのですが、消化に時間がかかるものを食べると、睡眠中に胃に食べ物が残り続けることとなります。
揚げ物や油を多く使ったメニューは、可能な限り昼食に食べるように心掛けましょう。
食べる量:消化に悪いものでなくとも、大量に食べると胃で消化しきれずに残ってしまいます。
普段から暴飲暴食には注意して、バランスの良い量を摂るようにしましょう。
タンパク質は適量を摂取することが大切
タンパク質は適量を:肉や魚、大豆などのタンパク質を摂取しないと、アミノ酸が少ない状態になります。
タンパク質を摂取することで身体のインスリンを変え、アミノ酸を循環させる働きがあります。
アミノ酸は、セロトニンとメラトニンの両方に関係しているので睡眠に影響を与えます。
特にベジタリアンなどでタンパク質をほとんど摂取しない…というのは注意が必要です。
【お悩み別】食事から眠りへの効果的なアプローチとは?
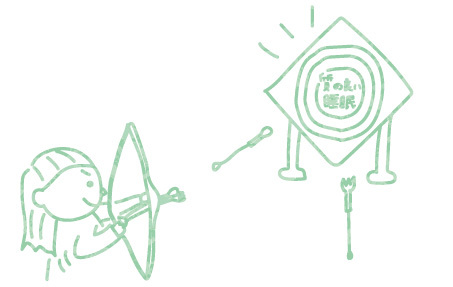
睡眠の悩みは多角的であり、それぞれの原因が複数重なっていることが多いのですが、悩みの原因を探り、食事の面からも可能なアプローチをしてみましょう。
朝スッキリ起きられない
寝付きの悪さや睡眠途中での覚醒が重なって起床時に目覚めが悪いと感じる方も多いのではないでしょうか。
起床したらまず朝日を浴びて体内時計をリセットする習慣を作り、必ず朝食を食べましょう。
睡眠ホルモンの原材料となるトリプトファンは、体内で作り出すことのできない栄養素で食べ物から摂取するしか方法はありません。
主にタンパク質に含まれていますが、トリプトファンの摂取が少なければ、規則正しい生活を送っていても睡眠の悩みが出てくることもあります。
タイミングとしては朝食に取り入れると、夜はぐっすり眠ることができ、朝はすっきり目覚められることがわかっています。
トリプトファンが多く含まれる代表的な食材は、乳、チーズ・卵・納豆、豆腐、味噌、ナッツ類、バナナやアボカドなどです。
また、ビタミンB6はトリプトファンの吸収を促進させます。
ヒレ肉やささみなどの肉類、青魚などに多く含まれているので、上手く組み合わせて食生活に積極的に取り入れてみましょう。
眠りが浅い気がする
眠りが浅い気がすると感じる場合は、寝る前の飲食を控え消化管を休ませることで改善する場合があります。
ストレスや自律神経の乱れが原因として考えられるので、食事面では、精神の興奮を抑え、心身をリラックスさせる働きのあるGABAを含む食べ物を取り入れるとことをおススメします。
GABAは、発酵食品、キノコ類、雑穀類、トマトなどに多く含まれます。
キノコ類の中ではぶなしめじやブナピーに特に多く含まれているとされています。
摂取するのは夕食が好ましいタイミングといえます。
なかなか寝付けない
寝付きが悪い場合は、寝る直前の習慣を見直してみましょう。
寝る直前の食事や、アルコール・カフェイン等の摂取は禁物です。
就寝3時間前から、食事やカフェインを含む飲み物は控えるようにするとよいでしょう。
また深部体温を下げて眠りに入りやすくしてくれる栄養素のグリシンを多く含む食材を夕食に取り入れるのも◎肉類や魚類をバランスよく摂取しましょう。
さらに良い睡眠のために効果的にグリシンを摂取する場合は「寝る前に3gがベスト」だといわれています。
グリシン3gを寝る前に摂っても胃の負担になりにくい食材に換算すると、100ccのホットミルクに5gのきな粉を溶かして飲めば3gのグリシンを摂取できることになります。
まとめ

質の良い睡眠を得ることで、日中は活動的に動くことができ、仕事や勉強のパフォーマンスも上がります。
眠っている間に分泌される成長ホルモンは、身体の回復のほかストレス軽減、肥満抑制や肌質の改善などにも高い効果を発揮します。
睡眠の質を高めるには、生活環境や睡眠環境を整えることはもちろん、食事面で身体の内側から整えてあげることも大切です。
「なかなか寝付けない、朝スッキリ起きることができない…」そう感じるときは、毎日の食事を見直すことから始めてみるのもいいかもしれません。
食事の習慣を整えるとともに、不足している栄養素を把握し、少しずつ改善を目指してみましょう。
今回の記事では眠りと食事にまつわる情報を記しましたが、食事以外の快眠方法にもご興味がある方は「睡眠を改善しませんか?質の高い眠りを手に入れる方法」をご参照ください。
本記事では、睡眠の質改善の方法や心身の健康を保つポイントなどをご紹介しております。気になる方はぜひご一読ください。
|
関連記事 |
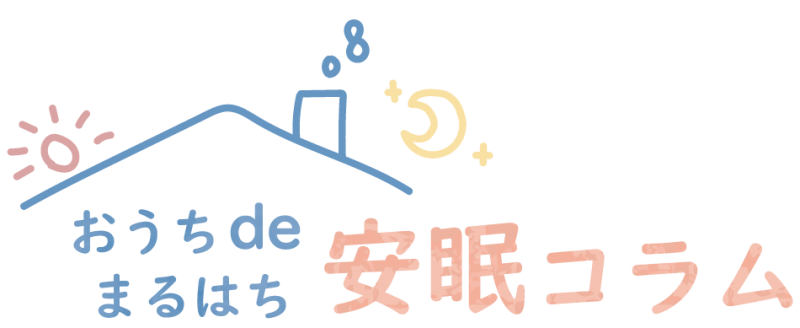 寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載
寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載
新着記事