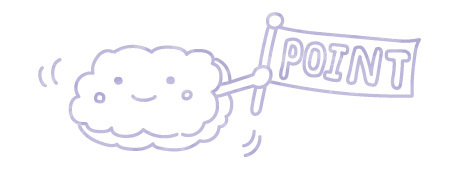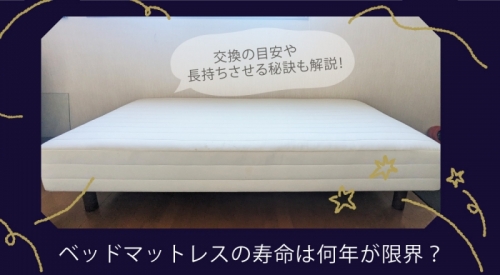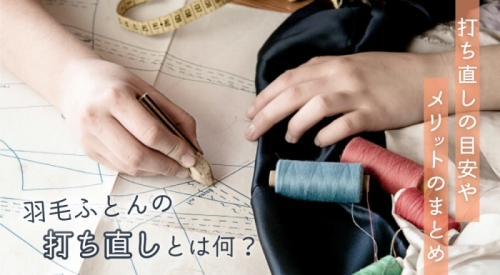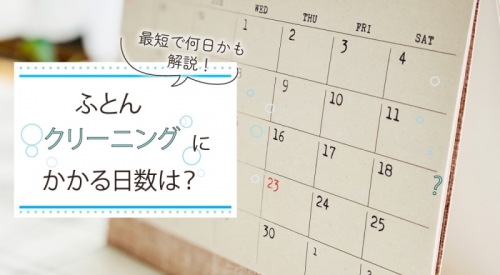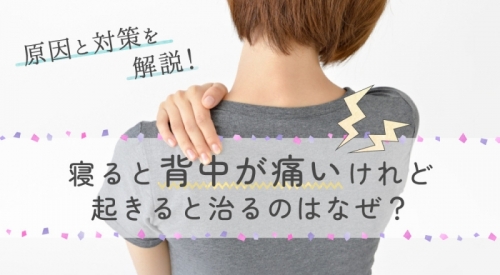|
羽毛ふとんの買い替えサインとは?

羽毛ふとんは一生ものといわ れることもありますが、羽毛ふとんにも寿命があります。
使う方の汗や皮脂の量や寝室・収納の環境にもよるので一概にはいえませんが、特別なメンテナンスをしないで使い続けている場合は、10年〜15年程度が寿命と考えるのが一般的です。
使用年数以外にも羽毛ふとんの買い替えサインは他にもあります。順番に解説していきます。
側生地の汚れ・傷みがある
カバーをつけて使用していても長年使っていると人の汗や皮脂、角質などの汚れによってふとんの側生地が汚れてしまうことがあります。
また、不意に食品や化粧品などをこぼしてしまったというケースも少なくありません。
ペットを飼っているご家庭ではふとんに粗相してしまうことも・・・。
そういったことが重なって汚れや生地の傷みにつながることがあります。
カバーを外してみて、ふとんをよくチェックして汚れや傷みが気になったら買い替えのサインと捉えても良いでしょう。
ふとんのボリュームが減った
長年使用していると羽毛が消耗し、購入時のようなふっくら感(かさ高)が徐々に減っていきます。
ふとんを干したり、ふとん乾燥機を使用しても、ふっくら感が戻らないときは、買い替えのサインと考えてもよいかもしれません。
購入したばかりのときは羽毛1つ1つにしっかりとハリがあり、この羽毛と羽毛の間に空気が溜まり、保温性を高めてくれます。
基本的に吸湿や放湿性が優れている羽毛ふとんは、汗や湿気などの水分を含んでも干したり、乾燥させることで通常はボリュームが元に戻ります。
しかし、長く使用していたり、汗や湿気が多い環境であると羽毛へのダメージが蓄積されるとかさ高が減少してしまう原因になります。
以前よりかさ高が減って、メンテナンスをしてもボリュームが戻らない場合は、羽毛ふとんの寿命のサインと判断してください。
羽毛の飛び出しや偏りがある
側生地から羽毛が頻繁に飛び出してくるようなら、側生地が劣化している可能性が高いといえます。羽毛ふとんは羽毛が出てこないようにするために、ダウンプルーフ加工という目詰め加工が施されています。
しかし、長年使用しているとダウンプルーフ加工が劣化し、羽毛が生地の織り目から出てきてしまうこともあります。
もし羽毛が大量に飛び出してくるのであれば、生地に穴が開いていたり、裂け目ができていたりする可能性もあります。
ですが、穴や裂け目があった場合でも針を使用して縫うのは余計に羽毛が出てくる原因になりますので、やめましょう。
応急処置にはアイロンで接着できる布製品用の補修テープ・布を使用するようにしましょう。
羽毛が飛び出してくる場合は、羽毛ふとんの寿命が近づいているサインになります。
また、日頃の使い方などによって羽毛が一方向に偏りやすくなることがあります。
さらにその状態が続くと、蓄積した汚れにより羽毛と羽毛がくっついてしまうので、元に戻りにくくなってしまいます。
ふとんを干したあと、反対方向に振ってみたり、軽く空気を抜いて羽毛が均等になるように叩いてならしても戻らないようなら買い替え時期を迎えているサインといえるでしょう。
保温性が下がってきた
羽毛ふとんは保温性が高く、軽くてしっかりあたたかさを感じられるのがよいところです。
しかし、長く使用したり、羽毛のかさ高が減ってきたりすると前よりもあたたかさを感じにくくなります。
「保温力が持続しなくなった」などと感じたら寿命と捉えるサインと考えましょう。
また、汗や皮脂の汚れが羽毛に蓄積すると、羽毛の放湿性が悪くなり湿気を放出できずふとんが重く感じることもあります。
ふとんが重いと身体が疲れやすくなり、快適な睡眠の妨げになります。
保温力の低下やふとんの重さが気になる場合は、1度羽毛ふとんのカバーを外してその他にボリューム感や羽毛の飛び出しなど当てはまる部分はないか羽毛ふとんの状態を観察してみましょう。
臭いが気になる
人間はひと晩に約コップ1杯分の汗をかいています。この汗や付着した皮脂をメンテンナンスせずにいると、汚れが蓄積して酸化してしまい、気になる臭いへと変化することがあります。
また、お子さんのおねしょやペットの粗相の処理が上手くいかず臭いの原因になっている場合や食べ物・飲み物を誤ってふとんにこぼしてしまった際の対処が甘かったりすることも考えられます。
通常であれば洗えば臭いもとれますが、長い期間使用しているとたまった臭いがとれなくなっているケースもあるので、その場合は寿命だと考えるポイントになります。
羽毛ふとんを処分する方法

羽毛ふとんを処分する場合は、大きく分けて以下のような方法があります。
処分する枚数やタイミングによっても適切な方法は異なりますので、ご自身の状況にあわせて参考にしてみてください。
買い替えをした際に回収してもらう
新しく寝具を購入した際に、店舗や販売店でそれまで使用していたふとんを引き取ってもらえる場合もあります。
ただ、期間が決まっていたり、対象商品が限られていたり、有料なこともあるので、購入する前にお店に必ず問い合わせをしてみましょう。
ゴミとして処分する
ふとん=粗大ゴミとして決められている地域では、事前に申込みをし、所定のシールを購入し、収集の日に合わせてゴミ捨て場に出しておけば回収してくれます。
特に立会いの必要もないので、準備さえしておけばOKです。
ふとんの枚数が多いなどの場合は、地域指定のゴミ処理センターへ自分で持ち込んで一気に処分する方法もあります。
この時は重さで金額が決まる場合や捨てるものの内容や大きさで決まる場合など、各自治体でルールが違うこともありますので、事前にきちんと問い合わせを行いましょう。
引っ越し業者や不用品回収業者に依頼する
処分を考える際が引っ越しのタイミングと同時の場合は、引っ越し業者の方で処分を行ってくれることもあります。
事前にふとんの処分をしたいことを伝えて料金など確認してみましょう。
また、引っ越し業者によっては対応していないこともあるので、必ず問い合わせをしてみてください。
他にも、不用品回収業者に依頼をする方法があります。
日付を自分で決定することができ、即日対応してくれる業者もあります。
処分を急いでいるときやふとん以外にも不用品を処分したい場合は、一度に処分できるため不用品回収業者の利用が適しているでしょう。
回収には料金がかかり、その料金は見積もりによって決まります。
業者によっても価格が異なるため、料金を比較しておくことをおススメします。
ただ、ふとんだけを処分する場合は割高になる可能性もあります。必ず確認しておきましょう。
羽毛ふとんを再生・リサイクルする方法

羽毛という素材の特性上、再生やリサイクルをすることができます。
ただ捨ててしまうのはもったいないと感じる方にはおススメの方法です。
お持ちの羽毛ふとんの状態を確認し、再生・リサイクルが可能な場合は1度検討してみるのもよいでしょう。
打ち直し(リフォーム)をする
羽毛ふとんを使用してから15年以内で、中のダウン率が70%以上のものであれば、羽毛の打ち直し(リフォーム)を検討するのも1つの方法です。
ふとんの打ち直し(リフォーム)とはどんなものなのか詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
実は、ふとんの打ち直しにかかる料金は1万円台〜10万円を超えるものまでさまざまです。
それは新しくなるふとんの側生地の種類や、洗浄方法・足し羽毛の有無など、いくつかの要因が影響しています。
打ち直しの工程が煩雑であったり、質の高い洗浄方法だったり、高価な側生地で仕立てられていたりするほど値段は高くなります。
せっかく打ち直しをするのであれば、決して安ければよいわけではありません。
打ち直しをした羽毛ふとんをまた10年以上使用することを考えると安さばかりに気を取られていると、後悔することになるかもしれません。
打ち直しは大切なふとんをリフォームすること。
自分のニーズと料金が一致し、安心して任せられる打ち直し業者を選ぶことが重要です。
羽毛ふとんの打ち直しを考えているなら、「おうち de まるはち」をご利用ください。
日本羽毛製品協同組合が認定している工場で、1枚1枚丁寧に打ち直しを行っています。
洗浄方法は、最高グレードのプレミアムダウンウォッシュ仕上げがメインでしたが、最近新しいラインナップも登場しました。
詳しくは羽毛ふとんの打ち直しページをご覧ください。
リサイクル回収に出す
ダウン製品の回収・リサイクルを行う「Green Down Project」という企画に参加している企業にふとんを持ち込み、回収してもらうことも可能です。
条件としてはダウン率50%のダウン製品で、多少の穴あきや汚れがあってもOKだそうです。
回収の方法は回収BOXが設置されていたり、店頭受け取りなど場所によって異なります。
ふとん店やクリーニング店以外にアパレルブランドも多く参加しており、店舗ごとに持ち込みできるダウン製品が決まっています。
Green Down Projectの参加企業であればどこでも羽毛ふとんを回収してもらえるわけではないので注意が必要です。
全国のGreen Down Projectの参加企業は公式ページから確認ができます。
羽毛ふとんを長持ちさせるために気をつけること
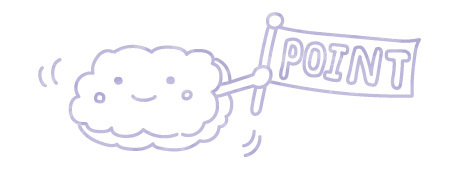
日頃から羽毛ふとんを良い状態で長く使用するために注意すべき点はどんなことがあるでしょうか。
順番にご紹介していきます。
カバーをつけて使用する
羽毛ふとんは、必ず掛けふとんカバーをかけて使いましょう。
掛けふとんカバーを必ず掛ける理由は、側生地の保護がメインにあります。
カバーを掛けずに使用すると汗や皮脂汚れがダイレクトにふとんの側生地にうつってしまい、劣化を早める原因になります。
また、外に干す際もカバーをつけると紫外線で日焼けするのを防いでくれます。
湿気をためない工夫をする
掛けふとんカバーを洗濯する際などに、部屋の中で陰干しをしましょう。
陰干しとは、風通しの良い場所に掛けふとんを広げるか、ふとん干しに掛けて、通気をさせて湿気を発散させることです。
ふとんを保管する際にもカビやダニは高温多湿の環境を好むため、しっかりと温度管理を行い、ふとんを保管している場所を高温多湿の環境にしないように気をつけなければいけません。
とは言っても押し入れやクローゼットで保管する場合には、湿度や温度の管理を徹底するのは難しいのが現実です。
そのため、定期的に換気を行い、収納している場所の空気の入れ替えをするようにしましょう。
収納時に圧縮袋を使用したり、上に重いものを置かない
羽毛ふとんには、圧縮袋は使わないでください。圧縮袋やビニール袋は湿気をためてしまうので、通気性のある不織布や風呂敷に包んで保存するのが基本です。
圧縮袋で湿気がこもり、ふとん本来のボリュームが元に戻りにくくなります。
特に羽毛ふとんは羽毛が空気を含むことで暖かさを保つので、機能が落ちてしまい、ふとん本来の弾力を失ってしまうので、専用の収納ケースを使用しましょう。
また保管の際は、かさばるからといって羽毛ふとんの上に重たいものを置いてしまうと羽毛が、細かく壊れてしまう原因になります。
ふとんを積み上げて保管するときは、重いふとんを下に、軽いふとんを上にしましょう。
マットレスや敷きふとんは下に、軽い羽毛ふとんは上に重ねることで、湿気もこもりにくくなります。
まとめ

古くなった羽毛ふとんを処分する方法は複数あるので、ご自身に適した対処法を考えることが大切です。
また、羽毛という素材の特性からリサイクルをすることができるので、リサイクルしたものをまた自分やご家族が使うのか、他の誰かの役に立つための行動をするのかなどを検討できるのも大きな特徴です。
今まで毎日の眠りを支えてくれた羽毛ふとんに敬意を込めて、手放すときにもベストと思われる選択をしてあげてくださいね。
|


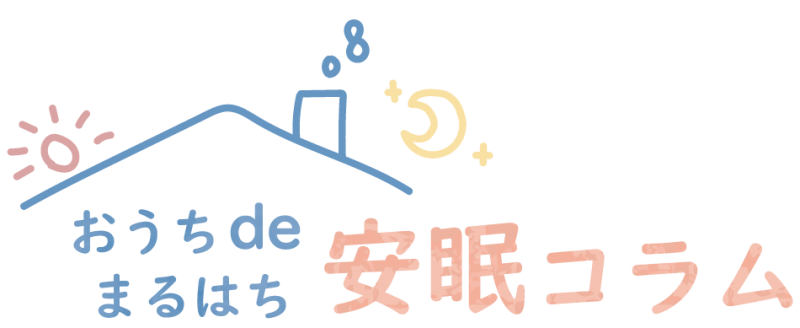 寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載
寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載