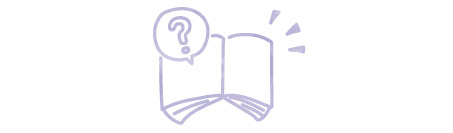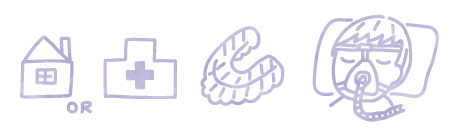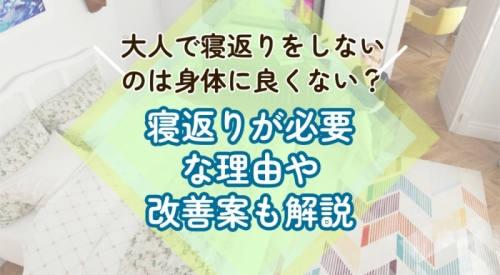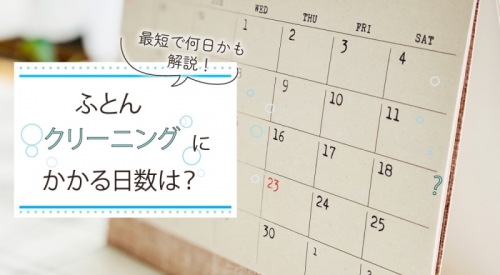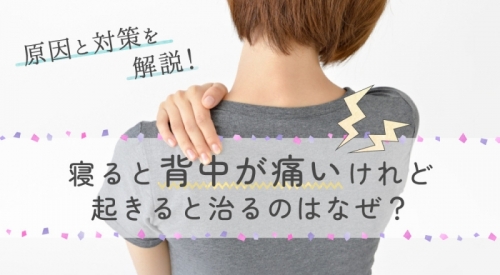あなたや家族は大丈夫?! 睡眠時無呼吸症候群とは?症状や原因などを解説
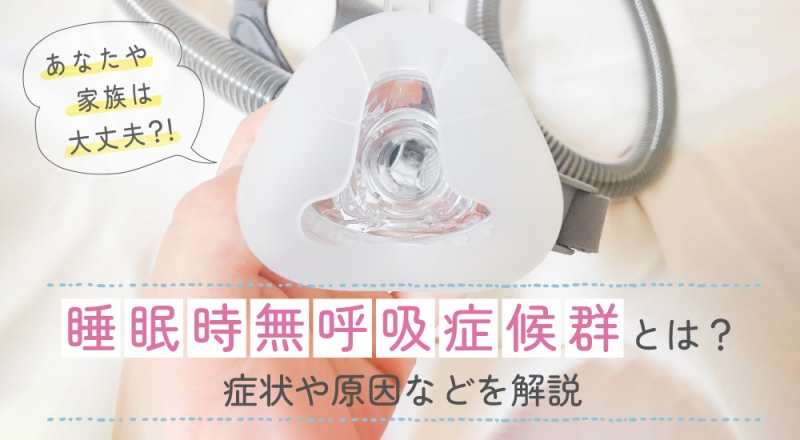
|
皆さんは寝ている間に自分や家族が 「大きないびきをかいていると思ったらいきなり呼吸がとまった」 「何秒か呼吸していない状態だったのか息苦しくて起きた」 などという経験はありませんか?
何日も続いたり、気になるようならそれは「睡眠時無呼吸症候群」かもしれません。 この病気は、寝ている間に生じる無呼吸が、起きているときの活動に様々な影響を及ぼします。 寝ているときは気がつきにくいですが、違和感を放置してしまうと日常生活に様々なリスクが生じる可能性があります。
このコラムでは、睡眠時無呼吸症候群について症状やチェックの仕方、原因から予防・治療法まで詳しく解説していきます。 |
睡眠時無呼吸症候群とは? |
|
● 大きないびきをかく ● 呼吸が⽌まる(と指摘されたことがある) ● 呼吸が乱れる ● 息苦しくて⽬が覚める |
起きたとき
|
● 口が渇いている ● 頭が痛い ● 熟睡感がない ● すっきり起きられない ● 身体が重いと感じる |
日中活動しているとき
|
● 運転中や会議中などに眠気に襲われる又は居眠りをしてしまう ● 記憶⼒や集中⼒が低下している ● しっかりと睡眠時間を確保しているのにだるさや疲労感を感じる |
この中の時間帯別(眠っているとき、起きたとき、日中活動しているとき)で各1つ以上当てはまる場合は睡眠時無呼吸症候群の可能性がありますので、専門の医療機関を受診しましょう。
こんな方は要注意?!なりやすい傾向をご紹介
睡眠時無呼吸症候群の発症に大きく関わっている要因として「肥満(メタボリック症候群)」があげられます。
BMI値の高さや首の太さに比例して発症する人の割合が高くなることがわかっており、こういった体格の方は首やのどにも脂肪がついて気道部分が狭くなるので、いびきの大きな原因になります。
さらに体重が増えると同時に酸素の必要量が増えますが、それに対して酸素の吸入量が減るために呼吸の回数と深さが増え、よりいびきが大きくなっていきます。
脂肪の影響で狭まった気道をさらに舌根が塞ぐことにより、呼吸の際の空気の通過が阻害されることでもいびきが発生し、完全に気道が塞がってしまうと睡眠時無呼吸症候群になります。
また、単純に考えると「肥満(メタボ)」→「睡眠時無呼吸症候群」→「眠りが浅い」→「代謝が悪い」→「太りやすい」→「肥満(メタボ)」という悪循環が起こります。
この計算方法で肥満と判断したら、要注意です。
≪肥満度の計算方法≫
体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)=肥満度 18.5〜25.0が標準で、22が理想的とされています。
25.0以上は肥満といえます。
上記の他に睡眠時無呼吸症候群になりやすい傾向をご紹介していきます。
骨格や体格
|
● 首が短い ● 首が太く、脂肪がついている ● 下顎が小さい、小顔 ● 歯並びが悪い ● 舌や舌の付け根が大きい |
生活習慣・体質
|
● 日常的にアルコールを摂取して、そのまま寝ることがある ● タバコがやめられない ● 暴飲暴食をしてしまう ● 高血圧や糖尿病などの既往歴がある ● 鼻炎やアレルギーで鼻がつまりやすい |
性別や年齢
|
● 男の方が多く発症しやすい病気といわれている ● 男性の罹患年齢は主に40~60代 ● 女性の場合は中高年以降の発症が増加傾向 ● 子どもの場合もアデノイド肥大や扁桃肥大、あごが小さい、肥満などで気道が塞がることが主な原因で発症することがある |
骨格や体格、生活習慣や体質、そして性別や年齢に関わらず、睡眠時無呼吸症候群を発症するリスクがあると考えられます。まさか自分がと思わずに、気になる場合は積極的に医師に相談することも大切です。
睡眠時無呼吸症候群の予防方法
生活習慣を改善したり、睡眠中に少し工夫をすることで予防効果が高まります。
順番にご紹介していきます。
減量を行う
前項の通り、肥満やメタボリック症候群が原因の場合は、減量を行うことで改善や予防につながります。
さらに減量することで合併する病気や生活の質の改善、心臓や血管の病気リスク低下などのメリットもあります。
禁煙・禁酒をする
喫煙や飲酒によって睡眠時無呼吸症候群が悪化することがあるため、禁煙・禁酒が推奨されています。
アルコールを摂取することで喉の筋肉がゆるみ、気道が狭まり、いびきをかきやすくなる原因にもなりますので注意が必要です。
寝姿勢を変える
仰向けに寝ると重力の影響で気道がふさがりやすくなってしまうので、身体を横向きにし、体位を変えることで気道を確保する方法を1度試してみてください。
また、抱き枕を使う方法も横向きでの睡眠をサポートすることができて、舌根沈下を防げるため、いびき防止につながります。
いびき防止グッズを使う
鼻腔拡張テープは鼻づまりが原因でいびきをかいてしまう鼻いびきの方におススメです。
貼ることで鼻の通りが良くなり鼻呼吸がしやすくなります。
口に貼るテープは鼻づまりがないのに口呼吸をしてしまう口いびきの方におススメです。
テープで口を閉じることにより自然な鼻呼吸ができて、いびきがかきにくくなります。
こういったいびき対策グッズを使用することでいびき・無呼吸の防止が期待できます。
睡眠時無呼吸症候群が軽症の場合は、減量や生活習慣の見直しだけで症状が改善することもあります。
しかし、ある程度症状が進んでしまったという場合は、極端な眠気のために気力が低下し、減量や生活習慣改善にもなかなか前向きに取り組むことができないこともありますのできちんと検査をして医師に相談するのが良いでしょう。
治療することによって睡眠の質がよくなると、減量や生活習慣の改善にも前向きに取り組めるようになり、症状改善の相乗効果が期待できます。
放置すると危険!睡眠時無呼吸症候群のリスクとは
交通事故
睡眠時無呼吸症候群ときいて1番に思い浮かぶリスクが「交通事故」ではないでしょうか。
日中に極端な眠気に襲われる睡眠時無呼吸症候群が原因の居眠り運転による大きな事故も数多く報道されています。
睡眠時無呼吸症候群の重症度が高いほど、短期間に複数回の事故を起こすといわれています。
なかでも、1人での運転、高速道路や直線道路の走行中、渋滞で低速走行中などに居眠り運転による事故が発生しやすくなっているとの報告があります。
社会生活の低下
仕事での重要な商談や会議中、学校での授業中などに強い眠気に襲われたり、居眠りをしてしまうことがあります。
仕事や勉強への意欲だけでなく、集中力や記憶力も低下し、周囲からは「怠けている」「だらしない」とみられてしまいメンタルのバランスも崩れてしまいます。
さらに、労働災害や産業事故につながった事例もあり、その損害賠償や環境汚染なども含めた損失は膨大なものとなる可能性があります。
合併症
睡眠時無呼吸症候群は生活習慣病と合併しやすく、代表的なものが高血圧と糖尿病といわれています。
通常、就寝中は脳がリラックスした状態にあり、副交感神経が優位に働いていますが、無呼吸を繰り返すことで脳が目覚めて交感神経の働きが活発になります。
また、無呼吸と呼吸の状態が細胞を酸化させてしまいストレスによる影響を受け、血管が傷つきやすくなり、血圧を上昇させる要因となります。
さらに年齢や肥満の有無にかかわらず糖尿病になりやすく、無呼吸状態による低酸素状態が末梢神経障害など、糖尿病合併症の発症リスクになる可能性も指摘されています。
また、お子様の場合には、成長ホルモンの分泌が阻害されることで発育に悪影響を及ぼしたり、胸部の変形、最悪のケースでは小児突然死症候群の原因になることもあるとされています。
睡眠時無呼吸症候群の検査方法と治療法
「もしかしたら睡眠時無呼吸症候群かも?」と思ったらどこを受診したら良いのでしょうか?
実は検査と治療ができる医療機関は全国にあります。
医療機関によって「睡眠外来」や「睡眠センター」のような専門の外来を設けている場合もあれば、内科、呼吸器科、循環器科、耳鼻咽喉科などが対応している場合もあります。
あるかわからない場合は、まずはかかりつけの医師に相談してみるのも良いかもしれません。
一般的な検査方法の流れ
検査方法は睡眠時無呼吸症候群の状況によって異なりますが、一般的なものを簡単に説明していきます。
①問診
まずは問診があり、起きている間の自覚症状や生活状況について医師に伝え、昼間の眠気や既往歴や体調変化、特徴的ないびきの有無などの情報を共有します。
家族からいびきや無呼吸を指摘されて医療機関を受診する人も多く、家族からの情報も診断の重要なポイントとなります。
もし問診だけで問題ないとなった場合にも生活習慣病など睡眠時無呼吸症候群のリスクがある人は、生活習慣の改善が必要と指導されることもあります。
②スクリーニング検査
問診で睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合には、まず自宅で携帯型装置を使ったスクリーニング検査を行います。
スクリーニング検査は「簡易PSG検査」とも呼ばれ、携帯型の装置を就寝時に装着し、睡眠中の呼吸状態や心拍数、酸素飽和度などを調べます。
この検査は、自宅で検査ができる点が最大のメリットとされており、普段の睡眠に近いリラックスした状態でいびきや呼吸の状態の検査が可能です。
患者さん自身で検査装置を装着し、普段通りに就寝することで、睡眠中の呼吸状態などを記録します。
③入院検査
スクリーニング検査によって睡眠時無呼吸症候群の疑いがあり、さらに検査が必要と判断された際には確定診断のための精密検査を行います。
これは実際に1泊入院して検査を行います。
睡眠時無呼吸症候群の診察、治療を主に行っている医療機関には、ベッドなどを完備した専用の検査室があります。
就寝前に頭や顔、身体などの必要な部位にテープで電極を貼り付け、寝ている間の脳波や呼吸、眼球、筋肉や口鼻の気流の動き、睡眠時の姿勢などを細かく記録します。
映像や音声を記録し、検査担当者が睡眠中の状況を常時監視する場合もあります。
見られていると思うと緊張しますが、機器の装着による痛みなどの不快感はなく、睡眠時無呼吸症候群の影響で普段の睡眠の質が低下していることが多いため、就寝時間になればいつも通り眠れることがほとんどいわれています。
この検査で、1時間あたりの無呼吸低呼吸の回数(AHI)を確認し、確定診断を行います。
主な治療法
睡眠時無呼吸症候群の治療法には症状の度合いによって主に3つの方法があります。
①マウスピース治療
就寝中に顎が下がって気道が塞がるのを防ぐために、自分に合ったマウスピースを作って就寝時に装着する治療法です。
下顎を上顎よりも前に出すように固定させることで上気道を広く保ち、いびきや無呼吸の発生を防ぐ治療方法です。
軽症〜中等症の方やシーパップ療法ができない方に対して行います。
②シーパップ(CPAP)治療
シーパップ(CPAP)と呼ばれる装置を使った治療で、睡眠時にマスクを装着してそこから強力な空気を送り込むことにより気道が塞がるのを防ぎます。
装置はレンタルをするのが一般的で、日中の眠気が強い方や中等症〜重症の方に行われます。
③手術による治療
アデノイド肥大や扁桃肥大が原因で気道が塞がり、睡眠時に呼吸障害が起きている状況で、シーパップ療法ができない場合、手術を行うことがあります。
お子さんでアデノイドや扁桃の肥大が原因の場合は、手術が有効な治療といえます。
また、鼻づまりが原因で睡眠時無呼吸症候群になっている状況で薬による治療で効果がない場合には、手術を検討することもあります。
まとめ

睡眠には、心身の疲労を回復する働きがあります。
そのため、睡眠が十分にとれない状態が続くと、眠気や疲労を感じるだけでなく、さまざまな悪影響を及ぼすようになります。
さらに眠っている間に無呼吸状態が繰り返されると、身体に取り込まれる酸素の量が少なくなるので結果的に他の病気の原因になったり、日常生活に支障ができたりしてしまいます。
睡眠時無呼吸症候群は日中の活動中に「眠気」に悩まされることも多いので、本人への不本意な評価とともに、労働の生産性が低下するなど社会的な影響も少なくありません。
あなたや家族の命に関わる睡眠時無呼吸症候群は、予防や早期発見、治療が必要な病気です。 心当たりがある場合には早めに医療機関を受診して状況を理解し、改善に努めていきましょう。
関連記事
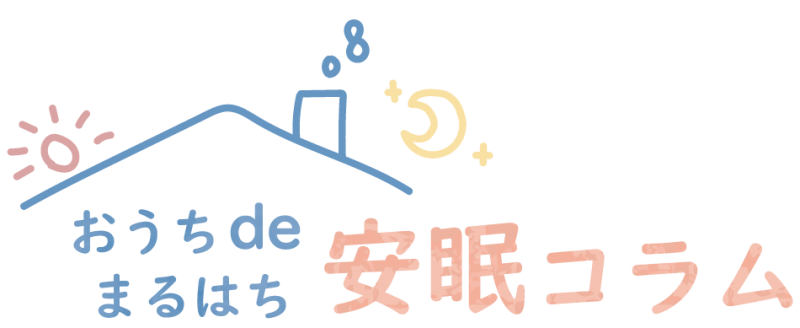 寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載
寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載
新着記事